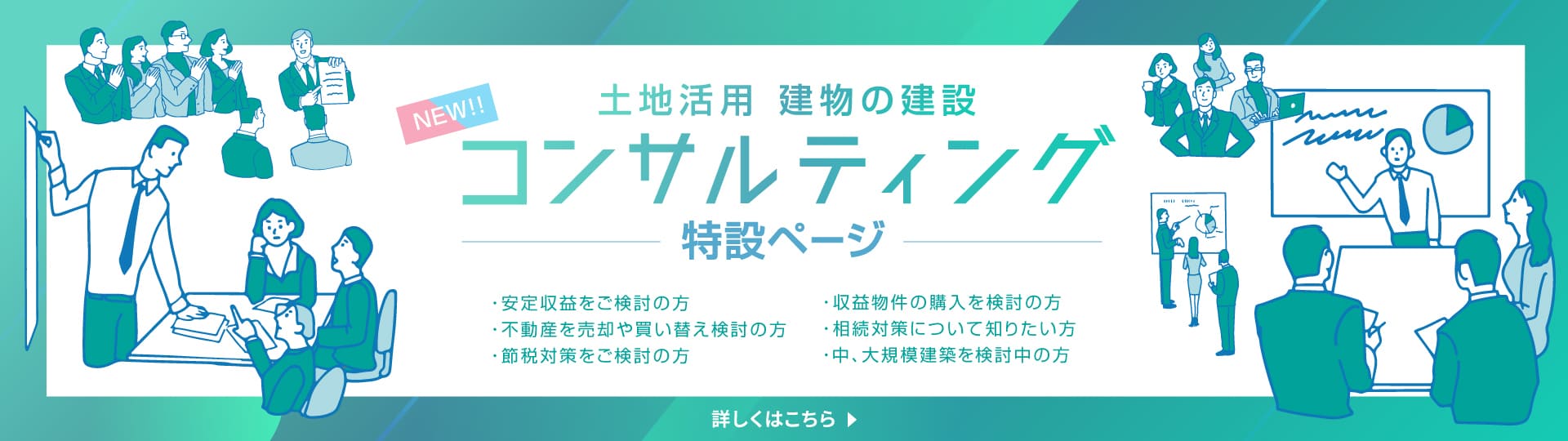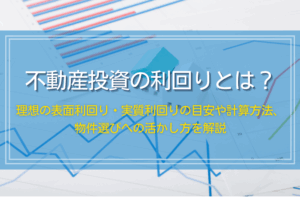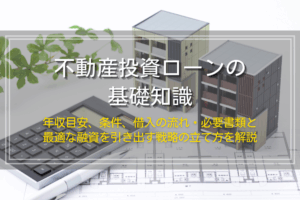投資用不動産の最適な売却タイミングはいつ?売却の流れや費用、税金を抑える方法も解説
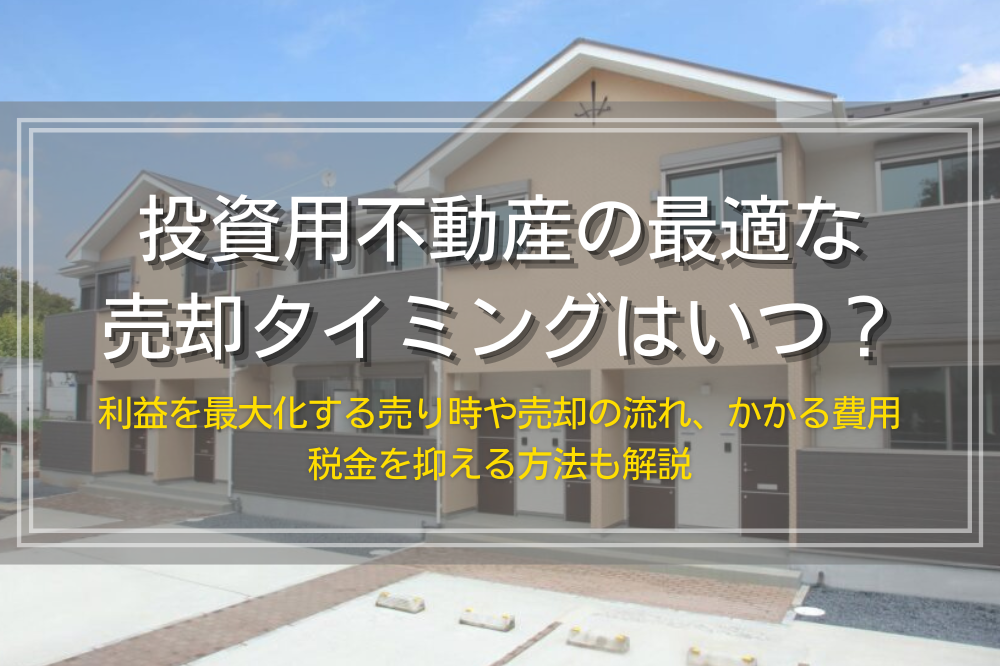
投資用不動産の売却は、最適なタイミングや方法を見極めることで、より大きな利益を得られる可能性があります。
このコラムでは、投資用不動産売却のベストなタイミングから具体的な流れや売却にかかる費用の内訳、税金を抑える方法などについて分かりやすく解説します。
不動産投資の買い換えや相続対策をお考えの方は参考にしてください。
コラムのポイント
- 投資用不動産の売却は、ご自身の投資戦略を踏まえ、所有期間や市場・物件の状況など、多角的な視点から最適な売り時を検討することがポイントです。
- 売却時の費用を抑える工夫や、売れ残り・価格下落のリスクに備えて対策することで、最大限の利益を確保することが可能です。
Contents
投資用不動産の売却タイミング・売り時はいつ?

不動産投資は、投資金額以上のプラスを得て投資を終える、または再投資で利益を拡大していくことが目的です。
つまり、これまでの家賃収入の累計と売却価格の合計が購入金額を上回る時が売り時と言えます。
上記を前提として、売却のタイミングとして検討したいポイントを解説します。
長期譲渡所得になるタイミング(所有期間5年以上)
不動産を売却した利益に対してかかる税金「譲渡所得税」は、物件の所有期間が5年以上になると税率が低くなり節税につながるため、売却の1つのタイミングと言えます。
〈譲渡所得税の税率〉
| 譲渡所得の種類 | 譲渡所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税率※ | トータルの税率 |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得
(譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える) |
15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
| 短期譲渡所得
(譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下) |
30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
※2037(令和19)年までは、「復興特別所得税」として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付する必要があります。復興特別所得税率は、長期譲渡所得が15%×2.1%=0.315%、短期譲渡所得が30%×2.1%=0.63%となります。
ただし、売却して損失が出るケースでは譲渡所得税は発生しないため、所有期間5年超を待たずに売却しても税金面で損をすることはありません。
また、節税効果をもってしてもカバーできない赤字が続くなら、5年超を待って損失が増える前に早めに売ってしまった方が良いケースもあります。
長期譲渡所得になるのを待って売却するのが有効かどうかは、物件の状況や投資戦略も踏まえて、不動産会社と相談の上決めることをおすすめします。
〈おすすめコラム〉
不動産売却で譲渡所得税がかからないケースとは|相続不動産売却・活用のポイントも解説
物件の市場価値が上がっている時
再開発が進んでいるなど、物件の需要が増えるような地域情勢の変化があった場合は、不動産の流動性が高まるため売却しやすくなるタイミングです。
通常、建物は年数が経過すると価値が下がりますが、需要が増え市場全体の不動産価格が上昇している時期であれば、購入時よりも高い値段で売れることもあります。
不動産市況をこまめにチェックし、売り時を見定めることで、より高値で売れる可能性を高められます。
減価償却期間が終了する前
建物の減価償却期間が終了し、所得の圧縮・節税効果が切れると、所得税が増えてキャッシュフローが悪化しやすくなるため、その前に売却するのも1つのタイミングと言えます。
減価償却が終了する前に売却すれば購入後もしばらくは税金が安くなるため、買主にもメリットになります。
築年数以外(利回りや入居状況、建物・管理状況)などの魅力を伝えて、妥当な価格であることをアピールするのがポイントです。
マンション・アパートの大規模修繕が近いタイミング
区分マンションなどでは、大規模修繕の前後で修繕積立金の値上げや一時金の徴収が予想される物件は購入を見送る人が増えるため、その前に売却するという考え方です。
逆に、大規模修繕を終えた物件は状態が良いと評価されやすいため売りやすいと考えることもできます。無理に大規模修繕を待つ必要はありませんが、売却する1つのタイミングとして覚えておきましょう。
投資用不動産の売却方法・流れ

アパートや区分マンション、戸建て賃貸などの投資用不動産を売却する方法、流れについて解説します。
①不動産の査定依頼
売却したい投資用不動産の価格査定を不動産会社に依頼します。
投資用不動産の評価方法は複数ありますが、将来的に生み出す賃料収入などの収益を基に価値を算出する「収益還元法」を用いるのが一般的です。
〈投資用不動産の評価方法の種類〉
| 評価方法 | 概要 |
|---|---|
| 収益還元法 | 将来得られる収益(賃料など)を基に物件の価値を算出する方法。
「直接還元法」と「DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)」の2通りがある |
| 積算法 | 土地の路線価や建物の再調達価格などを積み上げて評価する方法。
減価修正(経年による価値の減少)を加味して、現時点の価値を算出する |
| 取引事例比較法 | 対象物件と類似する不動産の過去の取引事例を参考にして価格を算出する方法。
築年数、立地、面積などを調整して比較し、市場性に基づいた評価が可能 |
| 原価法 | 土地と建物を個別に評価し、建物は再建築費用から減価償却費を差し引いて現在の価値を算出する、収益性ではなく物理的価値に着目した方法。 |
例えば、年間家賃収入が200万円、適正利回りが5%の投資用不動産の場合、収益還元法(直接還元法)を用いると物件価格は200万円÷5%=4,000万円と算出できます。
査定価格が妥当かどうかを判断するためにも、投資物件情報サイトなどで周辺の投資物件の売り出し価格や売却実績を調べることをおすすめします。
②不動産会社へ売却を依頼する
査定結果に納得したら、不動産会社へ実際に売却を依頼します。
不動産の仲介を依頼し、決済するまでの期間は約3~6か月が目安で、1年以上を要する場合もあります。
不動産会社との媒介契約は主に3種類あり、それぞれに特徴やメリット、向いているケースが異なります。
- 一般媒介契約:複数の不動産会社と契約でき、自分で見つけた買主と直接契約も可能
- 専任媒介契約:1社のみと契約し、自分で見つけた買主と直接契約も可能
- 専属専任媒介契約:1社のみと契約し、自分で見つけた買主との直接契約はできない
上記のように、媒介契約の種類によって契約できる会社の数や売却活動の制限が異なります。
一般媒介契約は複数の会社に仲介を依頼でき、親戚や知人など自分で見つけた買主とも交渉できます。また、不動産会社間の競争による業務の促進を図ることができ、買い手探しの範囲が広がるというメリットがあります。
1社のみと契約する専任媒介契約・専属専任媒介契約は、定期的な業務処理状況の報告義務があることから、積極的な売却活動が期待できるケースも。
どちらが良いかはケースバイケースなので、それぞれの特徴を把握して選びましょう。
買取の場合は買主を探す必要がないため、不動産会社の査定額に納得すればすぐに売却できます。オカムラホームの買取サービスなら最短10日で現金化が可能です。
〈おすすめコラム〉
空き家買取の基礎知識|メリット・デメリットや不動産会社選びのポイントを解説
③売却活動を行う
媒介契約締結後に、不動産会社による売却活動が始まります。
投資用物件でアピールすべきポイントは以下のようなものがあります。
- 収益性(利回り)
- 立地条件(エリアや駅からの距離、生活利便性、将来性など)
- 稼働状況(入居率や長期入居の多さなど)
- 建物状態(外観、内装、設備、配管など)
- 性能(ZEHや長期優良住宅、耐震等級など)
- 大規模修繕実施状況(実施年月日や予定、修繕内容)
- 管理状況
- 間取り
- 節税効果
築年数の古い物件のアピールポイント
築年数の古い物件は、外観や内装、設備、配管などの状態や修繕計画の履行状況、新耐震基準に適合しているかなど、建物や管理状態の良さをアピールして収益性が期待できることをアピールするのがポイントです。
多少の劣化などが気になる場合、インスペクション(建物検査)を受けて、あらかじめ不具合がある、今後発生する可能性がある部分を明確にしておく方法もあります。買主は正確な物件状態を踏まえた上で検討できるため、契約後のトラブル防止につながります。
また、木造の中古物件は1年あたりの減価償却費が大きくなるため、節税効果が高い点が高所得の投資家層へアピールになる場合も。
一棟アパート・区分マンションのアピールポイント
区分マンションは配置(日当たり、角部屋)などのメリットも伝えるようにしましょう。
入居者に人気の設備(エアコン、バストイレ別、追い炊き機能、独立洗面台、ロフトなど)がある場合もアピールポイントになります。
戸建て賃貸のアピールポイント
戸建ての場合は立地や物件状態、管理状況の他に、庭や駐車場の広さ、外部倉庫などの情報も重要になります。
また、エリアの需要を踏まえたアピールも大切です。
戸建て賃貸のニーズは基本的にファミリー層がメインですが、最近は平屋の一人暮らしや民泊、シェアハウスなども人気があるため、地域の賃貸需要をしっかり調査してアピールポイントを検討しましょう。
場合によってはフルリノベーションという選択肢もありますが、不動産会社としっかり相談の上、メリットが大きいかどうか判断してから実施するのがおすすめです。
逆に、DIY賃貸向けとしてなら、現況のままで売却できます。
オカムラホームでは売却前のリフォームやリノベーションの相談も可能です。
④買付申込~交渉
売却活動を始めて、購入希望者がいた場合には契約条件の交渉に入ります。
売却価格は不動産会社と相談の上、販売相手から値下げ交渉される可能性を想定して、少し高めに設定するなどの戦略を立てましょう。
売却益でローンを完済したい場合などは特に、あらかじめ値下げの許容範囲を決めておくのがおすすめです。
⑤不動産売買契約を結ぶ
売主・買主の同意が得られた場合、売買契約を締結します。
契約当日は、不動産会社が作成した売買契約書に署名・捺印します。売主は買主から手付金(売買代金の10%程度)を受け取り、不動産会社に仲介手数料の半金を支払うのが一般的。
オーナーチェンジ物件の場合は、賃貸借契約も買主に引き継がれます。
売買契約時には印鑑(実印・認印)や身分証明書、印鑑証明などが必要になります。
また、売買契約書に貼る収入印紙代は、売主・買主双方が負担するのが一般的です。
⑥引渡し(残金決済)
物件の引渡し当日は、平日の日中に売主、買主、不動産会社、司法書士などの関係者が集まり、決済手続きを行います。
決済時には、買主から売主へ手付金を差し引いた残りの売買代金が支払われ、売主は買主に書類一式や鍵などを渡します。投資用不動産ローンが残っている場合は、決済時に一括返済するのが一般的です。
アパートなどを月の途中で売却する場合は賃料の精算が必要です。
また、売主が入居者から預かっていた敷金は、買主に返還義務が引き継がれます。買主は、売買代金から敷金相当分を差し引いた額を支払うことで敷金を引き継ぎます。
その後、司法書士が法務局で所有権移転登記を行い、手続きが完了します。
⑥入居者へ賃貸人の変更を通知する(オーナーチェンジの場合)
オーナーチェンジによって賃貸人が変更された場合、入居者に対して「賃貸人の地位承継通知書」を送付するのが一般的です。
法的義務ではありませんが、賃借人に家賃の振込先や管理会社の変更を知らせていないと、トラブルの原因になる可能性があります。
通知書には以下の内容を記載します。
- 所有者変更(オーナーチェンジ)の報告
- 敷金返還義務の承継
- 賃貸契約条件の確認
- 新しい振込先と切り替え時期
- 新管理会社の連絡先
通知書は売主・買主の連名で作成し、不動産会社や管理会社が実務を担うことが多いです。
⑦必要に応じて確定申告をする
投資用不動産を売却して利益が出た場合は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をし、課税所得に応じた税金(譲渡所得税)を納める必要があります。
また、売却によって譲渡所得がマイナス(譲渡損失)となった場合、他の土地や建物の譲渡所得がある場合は、その金額から控除できます。
ただし、投資物件などの事業用不動産の損失は、マイホーム(居住用不動産)の売却時と異なり、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算できないため注意が必要です。
(参考)国税庁ホームページ|No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
不動産売却時の確定申告の流れや譲渡所得税の計算方法は以下のコラムで詳しく解説しています。
〈おすすめコラム〉
相続した土地や家を売った時の確定申告|自分でする流れや必要書類、申告不要なケースを解説
相続した不動産を売却する流れ|税金や必要書類、相続人同士での分割方法も解説
不動産投資物件の売却にかかる費用

譲渡所得税以外に、投資用不動産売却時にかかる費用を紹介します。
仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社に売却の仲介を依頼して買い手が決まった際に支払う手数料です。
不動産売買の仲介手数料は「宅地建物取引業法」によって上限額が定められています。
不動産の仲介手数料は、物件の売買価格によって以下のように上限額の計算方法が変わります。
不動産の仲介手数料上限額の計算方法(速算式)
| 売買価格 | 計算式(速算式) |
|---|---|
| 200万円以下 | (売買価格×5%)+消費税 |
| 200万円超〜400万円以下 | (売買価格×4%+2万円)+消費税 |
| 400万円超 | (売買価格×3%+6万円)+消費税 |
例えば、不動産を2,000万円で売却した場合、仲介手数料の上限額は2,000万円×3%+6万円+消費税で72万6,000円になります。
〈おすすめコラム〉
不動産の仲介手数料は売主・買主どちらが払う?支払いタイミングや相場、安くする方法も解説
印紙税
印紙税は、不動産売買契約書を作成する際に課される税金です。売買契約締結時に収入印紙を契約書に貼付し、印鑑などで消印することで納税します。
不動産売買契約書の印紙税は、令和9年3月31日までは記載金額が10万円を超える場合に以下の表の通り軽減税率が適用されます。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | -(非課税) | -(非課税) |
| 10万円以下 | 200円 | 200円(軽減なし) |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1千万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1千万円超5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
(参考)国税庁ホームページ|不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
登録免許税
登録免許税とは、不動産登記の際に課される税金です。
投資用不動産の売却時にはローンを組む際に設定した抵当権抹消手続きなどが必要なケースがあります。抵当権抹消手続きにかかる登録免許税は以下の通りです。
| 登記の種類 | 手続きが必要なケース | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 抵当権抹消登記 | 売却する不動産に抵当権が設定されている場合(ローンで購入した物件など) | 1つの不動産につき1,000円
(投資用不動産の場合、土地・建物それぞれの合計で2,000円) |
(参考)法務局ホームページ|住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)
また、不動産の所有者が変わると、住所変更や所有権移転登記が必要になります。
不動産売買では抵当権等の抹消費用、住所変更費用は売主が負担し、所有権移転及び抵当権設定費用は買主負担が一般的です。
不動産会社による媒介の場合、所有権移転登記の費用は買主負担とする特約を付けるのが一般的ですが、トラブルを防ぐために、契約書での登記費用負担に関する記載を売主、買主双方で確認してから契約することをおすすめします。
(登記を依頼する場合)司法書士報酬
抵当権抹消登記や所有権移転登記を司法書士へ依頼する場合は別途報酬を支払う必要があります。
司法書士へ依頼する際の報酬相場は、抵当権抹消登記が1万円〜2万円、所有権移転登記は3万円~6万円程度になります。
投資用不動産の売却にかかる税金や仲介手数料を抑える方法

前章で解説した通り、不動産投資物件の売却益にかかる譲渡所得税は、所有期間が5年を超えると税率が大幅に下がるため、負担を抑えられます。
その他、以下の方法でも売却時の費用を抑えられる可能性があります。
譲渡所得の計算で取得費・譲渡費用をもれなく計上する
譲渡所得税の計算で用いられる「物件購入にかかった費用(取得費)」「売却にかかった費用(譲渡費用)」をそれぞれ最大限計上することでも、課税所得を減らして税額を抑えられる可能性があります。
譲渡所得の計算式と取得費、譲渡費用の内訳は以下の通りです。
譲渡価額 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) = 譲渡所得(利益)
| 譲渡価額 | 不動産を売却した代金
(売却時の固定資産税・都市計画税の精算金も含まれる) |
|---|---|
| 取得費 | 不動産を購入する際にかかった金額の合計
|
| 譲渡費用 | 不動産を売却するために直接かかった費用
※修繕費や固定資産税などの維持管理費用や、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。 |
(参考)国税庁ホームページ|令和6年分確定申告特集|不動産等を売却した方へ
上記に挙げられている取得費や譲渡費用を漏れなく計上することで、課税所得を圧縮し譲渡所得税額を減らせる可能性があるため、購入当時の関係書類や領収書などはしっかりと保存しておくことをおすすめします。
課税所得を減らせる特例を利用する(相続した投資物件の場合)
アパートや貸地などの投資用不動産を相続した場合は、相続後一定期間以内に売却すると、譲渡所得税を軽減できる特例(相続税の取得費加算の特例)を適用できる場合があります。
(参考)国税庁ホームページ|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続した不動産投資事業を引き継がない場合は、上記の特例を適用して早めに売却することで税負担を軽減しながら物件を手放せる可能性があります。
また、要件を満たす事業用不動産を売却し一定期間内に買い換えると、売却益の一部に対する課税を将来に繰り延べる特例(事業用不動産の買い換え特例)を適用できるケースがあります。
(参考)国税庁ホームページ|No.3405 事業用の資産を買い換えた時の特例
事業用不動産の買い換え特例は、税金を買い換え後の不動産を売却する時まで繰り延べるのであって、非課税になるわけではありません。
ただし、特例適用によって買い換え直後の手残りを増やせるため、投資規模を拡大して将来の収益をさらに増やす可能性が高まるなどのメリットがあります。
〈おすすめコラム〉
相続した土地を3年以内に売却すると節税できる?「相続税の取得費加算」「空き家特例」の適用要件や手続き方法、注意点を解説
不動産会社の買取を利用して仲介手数料を抑える
不動産会社の買取サービスを利用すれば、短期間で現況のまま売却でき、仲介手数料もかからないため最低限の手間と費用負担で売却できます。
ただし、買取による売却価格は仲介による売却の一般相場より2~3割安くなることが多いなどの注意点もありますので、不動産会社と相談しながら最適な売却方法を選択するのがベストです。
買取と仲介の比較や買取を依頼する不動産会社選びのポイントは以下のコラムで詳しく解説しています。
〈おすすめコラム〉
空き家買取の基礎知識|メリット・デメリットや不動産会社選びのポイントを解説
投資用不動産の売却でよくある質問

最後に、投資用不動産、収益物件の売却でよくある質問についてまとめました。
不動産投資ローンが残っていても売却できる?
ローン残債のある不動産は、完済して抵当権を抹消してからでないと売却はできません。
また、売却価格がローン残債を上回る場合は売却益で完済できますが、下回る場合は不足分を自己資金や別途の借入等で用意しなければなりません。
不足分を用意できない場合、売却はできないため計画を見直す必要があるでしょう。
入居者がいても売却は可能?
入居者がいる物件は「オーナーチェンジ物件」と呼ばれ、売却は可能です。オーナーチェンジ物件では買主が賃貸借契約をそのまま引き継ぐ形になります。
買主は購入後すぐに収益を得られるため、入居率が高いオーナーチェンジ物件は売却しやすくなります。
入居者がいる物件は内見が難しい場合が多いため、物件管理状態や修繕計画を記載した資料やレントロール(賃貸借契約の状況をまとめた書面)、室内の写真などを準備することで買い手にアピールできます。
収益物件売却時に消費税は課税される?
不動産を売却する際に消費税がかかるかどうかは、売却する不動産の種類や売主の立場によって異なります。
まず、土地の売買では消費税は非課税となります。土地は消費されるものではなく、使用によって減少する(価値が変わる)ものではないためです。
建物部分に関しては、個人がマイホームを売却する場合は消費税はかからなりません。
一方、売主が法人や事業として継続的に売買を行っている個人などの「課税事業者」で、事業用不動産を売却する場合は、建物部分の売却金額に対して消費税が発生します。
不動産売却時に消費税が課される場合、売主は買主から消費税を受領した翌年に、税務署に「消費税及び地方消費税確定申告書」を提出して納税します。
提出・納付期限は原則として個人事業者は翌年の3月31日、法人は事業年度の終了日の翌日から2か月以内となっています。
売れ残りや価格下落などのリスク対策は?
不動産投資物件の売却において売れ残りや価格下落のリスクを避けるには、物件選定の時点から出口戦略の設計と事前準備が重要になります。
売却時のリスクへの主な対策は以下のようなものがあります。
資産価値の落ちにくい物件を選ぶ
駅近や築浅、管理状態が良好など、資産性が高く価格下落リスクが低い物件を選ぶことで、売却時にも買い手が見つかりやすくなります。
条件の良い物件は次の買主も融資を受けやすくなるため、より流動性が高くなり、売れ残るリスクを低減できます。
〈おすすめコラム〉
不動産投資初心者はどんな物件を購入すべき?初めての物件選びの失敗を防ぐ
運用中も建物の価値や収益性を高める工夫を
運用中の建物管理がしっかりしていて、収益性を高める工夫がされている物件は、投資家にとって魅力的となります。
計画修繕をしっかりと実行する、大規模修繕に向けて適切な修繕費積み立てを確保する、入居者に人気の設備・間取りを導入するなどの対策を随時打っていくことで売却時にも有利になります。
売却戦略(出口戦略)を早期に設計する
出口戦略を早期に設計しておくことで、売却時の選択肢と柔軟性が広がります。
オーナーチェンジで利回り重視の投資家に売る、更地化して再開発ニーズに応える、自己居住用として実需層に転用するなど、物件の特性と市場動向に応じた売却ルートを事前に整えておくことが、価格下落や売れ残りのリスク回避につながります。
〈おすすめコラム〉
不動産投資における「出口戦略」の重要性|売却のタイミングや成功のポイントを解説
不動産投資のリスクと回避策|安定収入を得て資産形成を成功させるコツを解説
まとめ
投資用不動産の売却は、ご自身の投資戦略を踏まえ、所有期間や市場・物件の状況など、多角的な視点から最適な売り時を検討することがポイントです。
また、売却時の費用を抑える工夫や、売れ残り・価格下落のリスクに備えて対策することで、最大限の利益を確保することが可能です。
オカムラホームでは、買い替え、資金確保、相続対策などの目的に応じた、最適な投資用不動産・収益物件の売却戦略を提案します。
無料査定、税金・諸費用の試算、市場動向に基づいた売却タイミングのアドバイス、仲介・買取の比較検討、売却後の資金計画まで一貫してサポートいたします。収益物件や相続不動産の売却を検討の際は、お気軽にお問い合わせください。