空き家を賃貸に出すメリット・デメリット|補助金活用や売却が良いケースについても解説
2025.09.20
2026.01.29

相続などで空き家を所有することになったものの、活用方法が分からず困っているという方もいるのではないでしょうか。「とりあえず維持しているけれど、毎年固定資産税がかかるだけ」「遠方に住んでいて管理も大変」といったお悩みは、決して少なくありません。
空き家をそのまま放置しておくと、税金の負担が増えたり、建物が傷んで資産価値が下がったりするリスクもあります。
そこで有効な選択肢の一つとなるのが、空き家を「賃貸」に出して家賃収入を得る方法です。このコラムでは、空き家を賃貸に出すメリット・デメリット、注意点を詳しく解説します。さらに、活用できる補助金制度や、売却が適しているケースについてもご紹介します。
コラムのポイント
- 空き家を賃貸に出すことは、資産を手放さずに継続的な収入を得られ、建物の劣化を防げるなど多くのメリットがあります。一方で、空室リスクや管理の手間、初期費用といったデメリットも存在します。
- ご自身のライフプランや物件の状況を考慮し、「賃貸」と「売却」のどちらが最適か、あるいはリフォームして自分で住むのかなど、他の選択肢も含めて総合的に判断することが重要です。
ご自身の状況に合った最適な空き家の活用方法を見つけるために、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
空き家を放置するリスク

具体的な活用方法を考える前に、まずは空き家を放置し続けることのリスクを理解しておくことが重要です。
経済的リスク
空き家は人が住んでいなくても、所有しているだけで固定資産税や都市計画税、火災保険料などの維持費がかかり続けます。
さらに、適切な管理がされていない「特定空家」や「管理不全空家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、税額が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。
物理的リスク
空き家は換気や通水がされないため、湿気がこもり、急速に老朽化が進みます。
建材の腐食や害虫の発生、雑草の繁茂などが進み、最悪の場合、倒壊して近隣に被害を及ぼす恐れもあります。
社会的リスク
管理されていない空き家は、ごみの不法投棄や不審者の侵入、放火などの犯罪の温床になりやすく、地域の治安悪化を招く原因にもなります。景観を損なったり、悪臭が発生したりして、近隣住民とのトラブルに発展するケースも少なくありません。
上記のようなリスクを回避するためにも、空き家は放置せず、早期に適切な対策を講じることが大切です。
〈おすすめコラム〉
管理不全空家とは?認定基準や特定空家との違い、固定資産税等のデメリットを回避する方法を解説
空き家の相続前に確認すべき5つのこと|デメリットを知ってトラブルを回避
空き家を賃貸に出すメリット

空き家を賃貸物件として活用メリットについて詳しく解説します。
資産を手放さず、安定した家賃収入を確保できる
空き家という大切な資産を売却することなく、毎月安定した家賃収入を得られるのが最大のメリットです。
得られた収入は固定資産税などの維持費や将来のための貯蓄、私的年金代わりにするなど、長期的な資金計画に役立てることができます。
人が住むことで建物の老朽化を抑制できる
前章で解説したとおり、家は、人が住まなくなることで換気が滞り、湿気などで急速に劣化が進みます。
賃貸に出して日常的に人の出入りや通水・換気が行われることで、建物の傷みを防ぎ、結果として不動産としての資産価値を維持することにつながります。
防犯性の向上と近隣トラブルの予防になる
人の目が行き届くようになるため、不法投棄や放火、不審者の侵入といった犯罪リスクを大幅に減らせます。
また、雑草の繁茂や害虫の発生も抑えられ、景観や衛生面での近隣トラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
ライフプランの変化に合わせた柔軟な活用が可能
賃貸は一時的な活用方法としても選択できるため、将来ご自身やご家族が住む必要が出た際には、自宅として利用できます。
売却とは異なり、「住まい」としての選択肢を手元に残しておけるのは大きな利点です。
税金の負担が増える「特定空家」指定を回避できる
適切に管理されず放置された空き家は、自治体から「特定空家」などに指定され、固定資産税の軽減措置が解除されてしまう恐れがあります。
賃貸物件として活用し適切に管理することで「特定空家」などに指定され、税負担が急増するのを防ぐことができます。
空き家を賃貸に出すデメリット

一方で、空き家を賃貸に出す際には、知っておくべきデメリットや注意点も存在します。
空室リスクがあり、収入が途絶える可能性がある
賃貸経営の最も大きなリスクは「空室」です。
常に入居者がいるとは限らず、退去してから次の入居者が決まるまで期間が空いてしまうと、その間の家賃収入はゼロになります。
特に戸建て賃貸は、アパートやマンションと比べて住戸数が一つしかないため、空室になった場合の影響が大きくなります。家賃収入がなくても、固定資産税や管理費などの支出は続くため、事前の資金計画が重要です。
管理の手間・コストがかかる
賃貸物件として貸し出すと、オーナーとして建物の維持管理責任が生じます。
給湯器やエアコンといった設備の修繕・交換、定期的なメンテナンス、入居者募集のための広告費など、さまざまなコストが発生します。
また、入居者からのクレームや騒音トラブル、家賃滞納の督促などの対応も必要です。
管理業務を不動産管理会社に委託することも可能ですが、その場合は管理委託手数料(一般的に家賃の5%前後)がかかります。
リフォームやクリーニングにまとまった初期費用が必要
DIY賃貸などを除けば、空き家をそのまま貸し出せるケースはまれで、多くの場合、入居者が見つかるようにリフォームやハウスクリーニングが必要です。
特に空き家期間が長かった物件や、築年数が古い物件は、水回り(キッチン、浴室、トイレ)の交換や壁紙の張り替え、外壁の補修など、大がかりな工事が必要になることもあります。
雨漏りやシロアリ被害など、目に見えない部分に問題が潜んでいると、想定外の追加費用が発生する可能性も。
1981年の建築基準法改正以前の建物は、耐震補強工事が必要になる場合もあります。これらの初期費用を回収するには一定の期間がかかることを念頭に置き、無理のない資金計画を立てることが大切です。
〈おすすめコラム〉
空き家対策はDIY賃貸が正解?貸主側のメリットや注意点をチェック
空き家をリノベーションして賃貸経営するメリット・デメリット|費用相場や注意点も解説
空き家は賃貸にするのと売却どっちがいい?

空き家を賃貸にする方法と売却する方法、それぞれのメリット、デメリットは以下のとおりです。
| 賃貸 | 売却 | |
|---|---|---|
| 収入 | 継続的な家賃収入が得られる | 一度にまとまった現金が手に入る |
| 資産 | 不動産という資産を持ち続けられる | 不動産資産はなくなる |
| 管理 | 管理の手間やコストがかかり続ける | 管理の手間や維持費から完全に解放される |
| 税金 | 固定資産税の支払いが続く | 固定資産税の支払い義務がなくなる |
| リスク | 空室・家賃滞納・災害などのリスクがある | 将来の値下がりリスクから解放される |
ご自身の状況に合わせて、どちらが向いているか判断しましょう。
賃貸が向いているケース
- 将来的にその家に住む可能性がある:いずれ戻る予定がある場合。
- 家や土地への愛着が強い:思い出のある家を手放したくない場合。
- 継続的な収入源が欲しい:安定した副収入を得て、家計や老後の資金にしたい場合。
- 物件の立地が良く、賃貸需要が見込める:駅近や商業施設の近くなど、借り手が見つかりやすい好条件の物件。
売却が向いているケース
- まとまった現金がすぐに必要:住宅ローンの返済や教育費など、急な出費に対応したい場合。
- 管理の手間やリスクから解放されたい:遠方に住んでいる、維持費の負担が重いなど、管理が困難な場合。
- 建物の老朽化が激しい:賃貸に出すには多額のリフォーム費用がかかる場合。
- 相続した物件で、遺産分割をしたい:相続人が複数いる場合、売却して現金化することで公平に分割しやすい。
未来の財託では、お客様一人ひとりのご状況やご希望を丁寧にお伺いし、賃貸・売却の両面から最適な活用プランをご提案いたします。空き家の査定や賃料のシミュレーションも無料で行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
空き家を賃貸として活用したいときに使える補助金

空き家を賃貸に出す際の初期費用は大きな負担ですが、国や自治体の補助金制度を活用することで、その負担を軽減できる場合があります。
リフォームやリノベーションで建物の価値を高めることで、入居者を惹きつけやすくなるため、積極的に活用を検討しましょう。(※以下は2025年9月時点の情報です。最新情報は各制度の公式サイトでご確認ください。)
既存住宅の断熱リフォーム支援事業
高性能な窓や断熱材を用いた省エネ改修を支援する国の補助金です。断熱性能を高めることで、光熱費の削減や快適性の向上につながり、賃貸物件としての付加価値を高められます。
- 補助上限額(戸建て):最大120万円/戸
(参考)公益財団法人北海道環境財団|【全国対象】既存住宅の断熱リフォーム支援事業
住宅セーフティネット制度による助成
高齢者や子育て世帯など、住宅の確保に配慮が必要な方の入居を拒まない賃貸住宅として登録(セーフティネット登録住宅)することで、バリアフリー改修や耐震改修などのリフォーム費用の一部が補助されます。
- 補助限度額:50万円/戸(工事内容により加算あり)
子育てグリーン住宅支援事業
既存住宅に省エネ改修や子育て対応改修等を行うリフォーム工事に対する国の補助金事業です。
要件を満たした躯体や開口部の改修をすることで、家事負担の軽減につながる設備や防犯性・防音性向上などのリフォームにも補助が出るため、負担を抑えながら物件の価値を大きく高められます。
- 補助上限額:1戸あたり60万円
先進的窓リノベ2025事業
高い断熱性能を持つ窓へのリフォームに特化した国の補助金事業です。窓の断熱性を高めることは、快適な住環境の実現に直結し、入居者への大きなアピールポイントになります。
- 補助上限額:1戸あたり200万円
自治体の空き家対策支援制度
国だけでなく、市区町村が独自に空き家対策の補助金制度を設けている場合があります。多くは自治体の「空き家バンク」への登録が条件となっています。
〈千葉県内の制度例〉
- 鎌ケ谷市:空家等リフォーム推進事業(補助対象経費の2/3、上限100万円)
- 旭市:空家活用支援事業(補助率2/3、補助限度額50万円)
- 富津市:空家バンク登録物件のリフォーム費用補助(補助対象経費の1/2、上限50万円)
※紹介しているのは2025年9月時点の情報です。最新情報は自治体の空き家対策支援制度を検索できるサイト等で必ず確認してください。
未来の財託では、補助金制度の活用も含めたリフォームプランのご提案も可能です。
賃貸にする以外の活用方法・解体で使える補助金や、売却時の減税制度などもあります。ご自身のケースに合わせて賢く制度を活用することで、初期費用や税金を抑えられます。
〈おすすめコラム〉
空き家に使える補助金と減税制度|活用・解体・売却などジャンル別に紹介
空き家賃貸を始める際に知っておきたい注意点と成功のポイント

最後に、空き家を賃貸に出す際に押さえておきたい注意点をまとめました。
物件や立地に合った用途で貸し出す
ひとくちに「賃貸」と言っても、一般的な住居用のほか、特定コンセプトのシェアハウス、地域に根差した店舗、あるいはトランクルームのような貸倉庫など、さまざまな活用法があります。
立地や周辺環境、建物の特性などを踏まえ、最もニーズが見込める方法を選ぶことが成功のポイントです。地域事情に詳しい信頼できる不動産会社に相談するのがおすすめです。
ローン残債がある場合は金融機関へ事前相談する
住宅ローンは、契約者本人が居住することを条件に融資されています。
そのため、ローン返済中の家を無断で賃貸に出すと契約違反になる可能性があります。必ず事前に金融機関に相談し、許可を得るか、事業用のアパートローンへの借り換えなどを検討しましょう。
入居前の状態を細部まで正確に記録・共有する
退去時の原状回復をめぐるトラブルを防ぐため、貸し出す前の室内の状態を写真や動画で詳細に記録しておきましょう。
傷や汚れの位置、設備の型番などを記録した「入居時チェックリスト」を作成し、入居者と相互に確認・署名しておくとさらに安心です。
知人に貸す場合でも「書面での契約」を徹底する
「知り合いだから」と口約束で貸してしまうと、家賃滞納や又貸しなどのトラブルが起きた際に対応が難しくなります。
親しい間柄であっても、必ず不動産会社を介するなどして、法的に有効な賃貸借契約書を作成しましょう。
不動産所得が生じたら毎年忘れずに確定申告を行う
家賃収入から必要経費(固定資産税、修繕費、管理委託料、減価償却費など)を差し引いた「不動産所得」が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。
申告漏れは追徴課税の対象となるため、忘れずに行いましょう。
〈おすすめコラム〉
家を貸す5つの方法|個人・戸建て賃貸・シェアハウス・民泊・貸倉庫
まとめ
空き家を賃貸に出すメリット・デメリットや、売却との比較、注意点について解説しました。
空き家を賃貸に出すことは、資産を手放さずに継続的な収入を得られ、建物の劣化を防げるなど多くのメリットがあります。一方で、空室リスクや管理の手間、初期費用といったデメリットも存在します。
大切なのは、ご自身のライフプランや物件の状況を考慮し、「賃貸」と「売却」のどちらが最適か、あるいはリフォームして自分で住むなど、他の選択肢も含めて総合的に判断することです。
「何から始めたらいいか分からない」「自分の場合はどちらが良いのだろう」
千葉県の八千代市、習志野市、船橋市およびその周辺エリアで空き家に関するお悩みをお持ちでしたら、地域に根差し50年以上の実績を持つ未来の財託にご相談ください。
未来の財託は、賃貸仲介・管理から売買仲介、リフォーム・リノベーションまで、不動産に関するあらゆるサービスをワンストップで提供する総合不動産会社です。
お客様にとって最善の選択ができるよう、専門知識豊富なスタッフが親身にサポートいたします。査定やご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

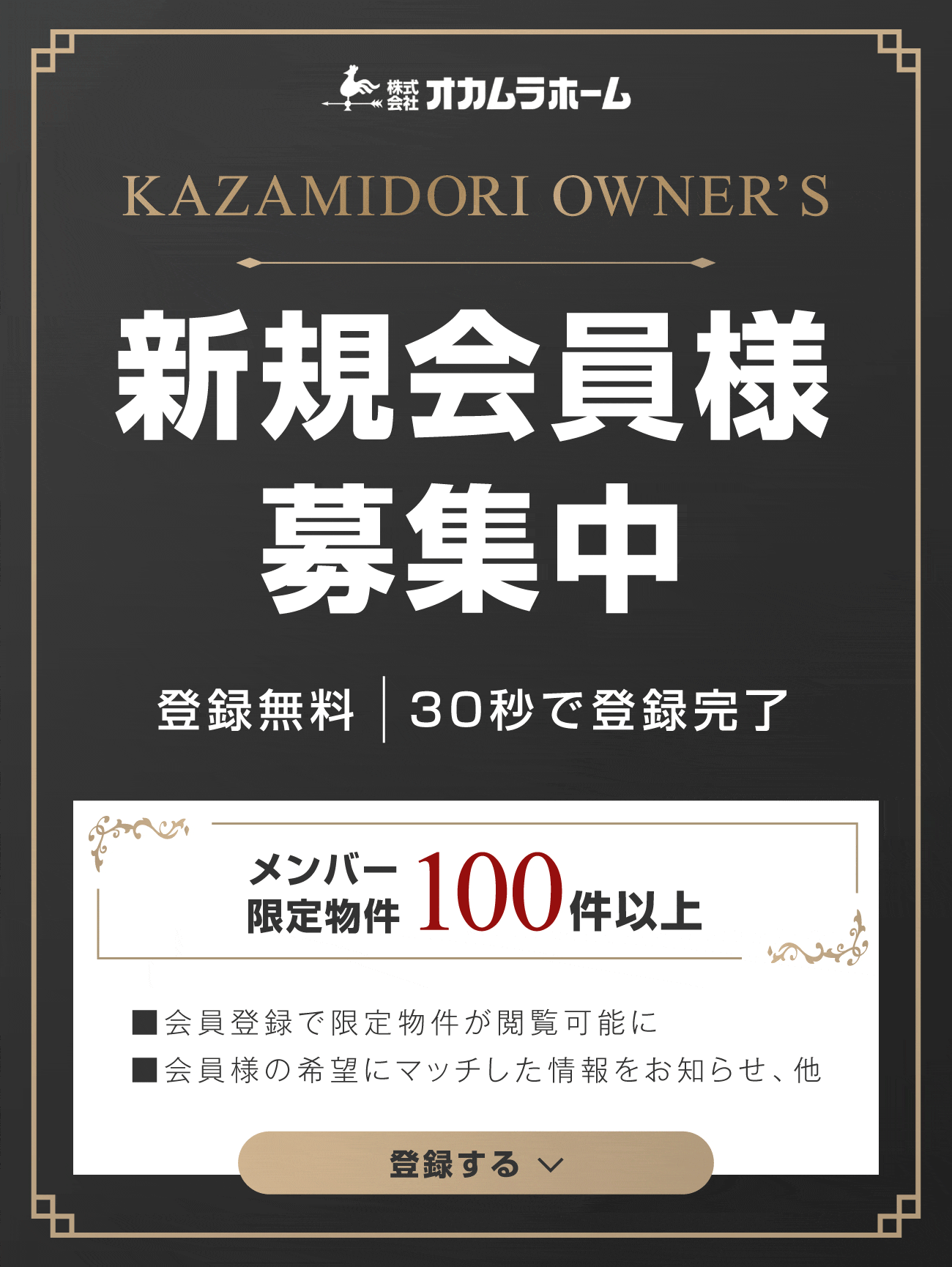

 0120-210-341
0120-210-341
