小規模宅地等の特例とは?要件や相続税の申告方法・添付書類をわかりやすく解説
2025.09.10
2026.01.29
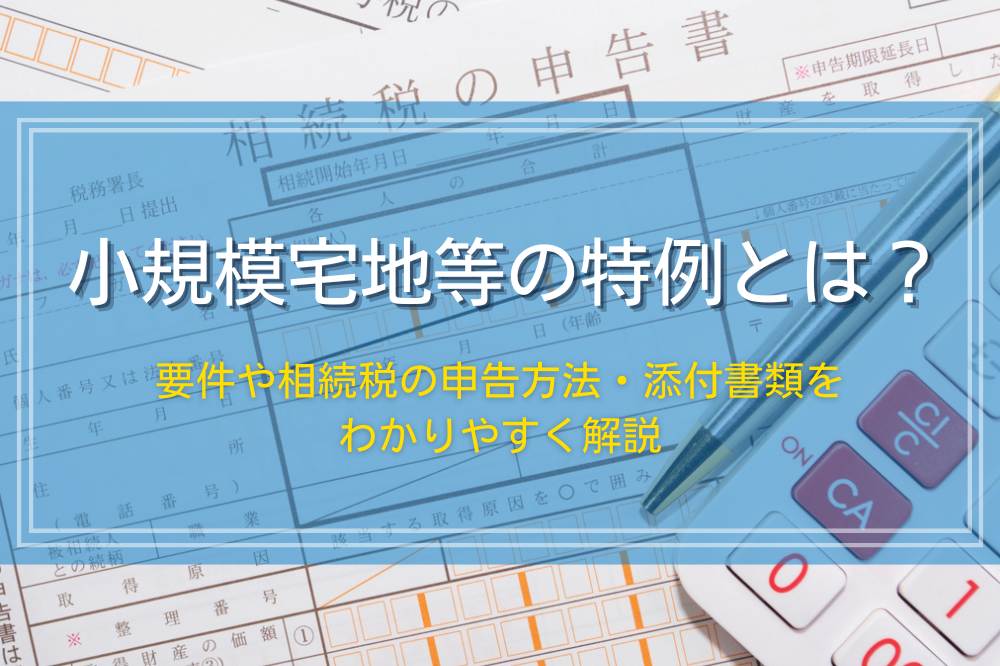
「親から実家を相続する予定だけど、相続税がいくらになるか不安…」
「相続税対策として、小規模宅地等の特例が使えると聞いたけど、よくわからない」
小規模宅地等の特例は、相続対策を考えている方、特に不動産を相続する可能性がある方にとって、必ず知っておきたい制度です。特例を適用できるかどうかで、相続税の負担が大きく変わる場合もあります。
このコラムでは、相続に不安を抱える方に向けて、以下の内容を分かりやすく解説します。
コラムのポイント
- 小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額を最大80%減額できる強力な節税制度です。
- 適用には「居住用」「事業用」「貸付用」などの種類ごとに、相続人の状況に応じた複雑な要件があります。
- 特に「家なき子特例」は要件が厳しく、生前からの準備や確認が不可欠です。
- 相続税が0円になる場合でも申告は必須であり、申告前の売却は原則NGなど、注意すべき点が多くあります。
特例を活用して節税効果を得るのはもちろん、相続した大切な資産を未来へつなぐための参考にしてください。
Contents
小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)が住んでいた自宅や、事業を営んでいた土地などを相続した場合に、一定の要件を満たすことで、その土地の相続税評価額を最大で80%減額できる制度です。
相続税は、財産の評価額を基に計算されるため、土地の評価額が80%減額されれば、納めるべき相続税も大幅に軽減されることになります。
小規模宅地等の特例がある理由
相続財産の中でも、自宅や事業用の土地は特に高額になりがちです。もし、この土地の評価額をそのまま用いて相続税を計算すると、税額が非常に高くなり、納税資金を捻出するためにせっかく相続した自宅や事業所を売却せざるを得ないという事態に陥りかねません。
小規模宅地等の特例は、残された家族が生活の基盤を失うことなく、安心して住み続けたり事業を継続したりできるようにするために設けられています。いわば「残された家族の生活を守るためのセーフティーネット」のような制度なのです。
国税庁のウェブサイトでも、この制度は「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」として紹介されています。
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(…)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、(…)割合を減額します。
小規模宅地等の特例を正しく活用することが、賢い相続対策の第一歩と言えるでしょう。
【ケース別】小規模宅地等の特例を適用できる4つの要件
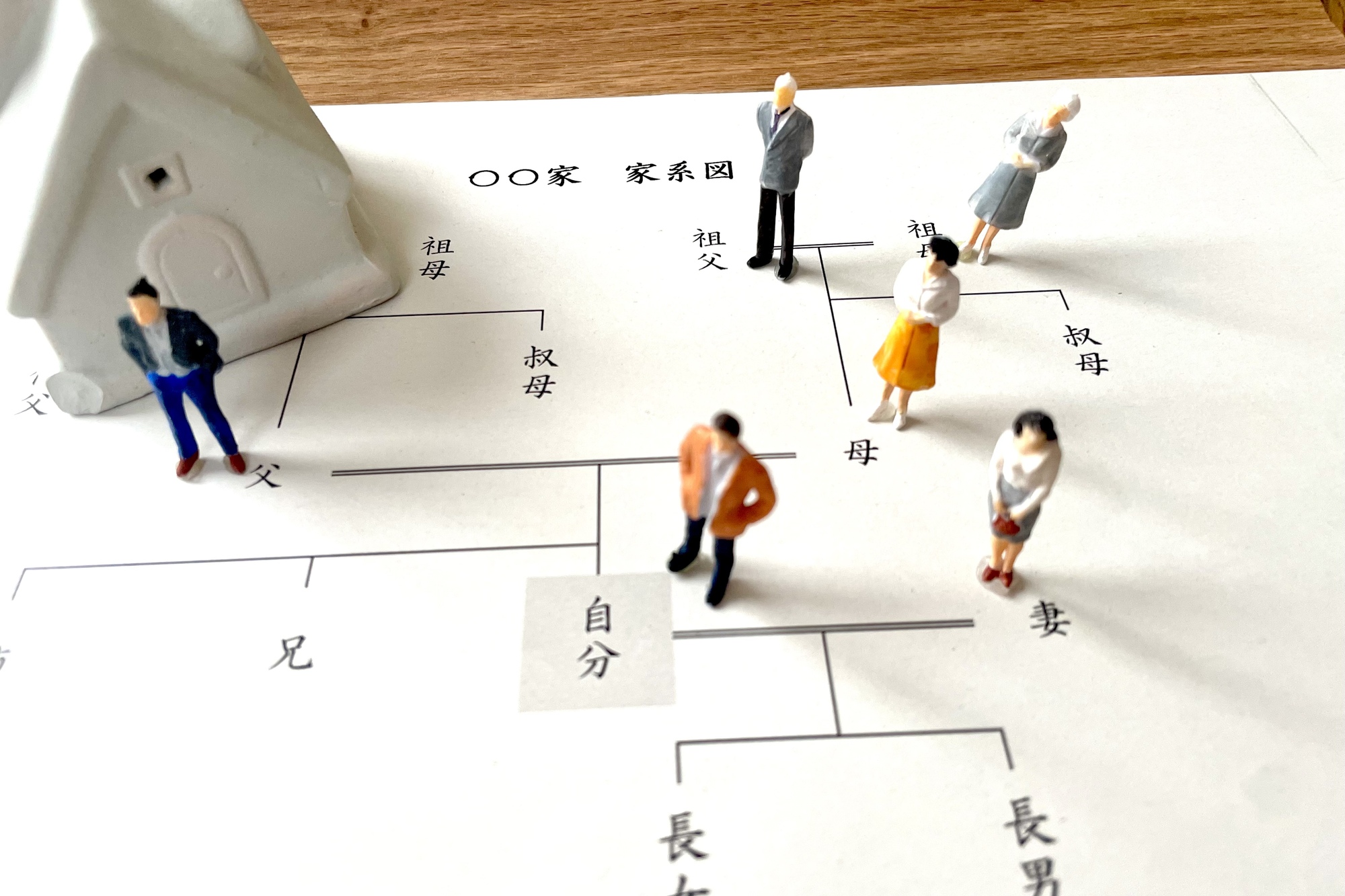
小規模宅地等の特例は、土地の利用状況によって大きく4つの種類に分けられます。それぞれ相続税評価額を減額できる割合や面積の上限、そして適用するための要件が異なります。
| 宅地の種類 | 相続税評価額の減額割合 | 限度面積 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 80% | 330㎡ | 被相続人等の自宅の敷地 |
| 特定事業用宅地等 | 80% | 400㎡ | 被相続人等の事業用の敷地 |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 80% | 400㎡ | 同族会社の事業用の敷地 |
| 貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ | アパート・駐車場などの敷地 |
ここでは、最も利用されるケースが多い「①特定居住用宅地等」を中心に、それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。
①被相続人の自宅の敷地(特定居住用宅地等)
亡くなった方が住んでいた自宅の土地を相続する場合に適用できるのが「特定居住用宅地等」です。減額割合が80%と非常に高いため、インパクトの大きい節税策となります。
ただし、誰がその土地を相続するかによって、満たすべき要件が細かく定められています。
土地を取得するのが「配偶者」の場合
配偶者が自宅の土地を相続する場合は、特別な要件なしで特例の適用が認められます。これは、残された配偶者の生活を保障するという制度の趣旨が最も強く反映されているためです。
土地を取得するのが「同居していた親族」の場合
亡くなった方と同居していた親族(子など)が相続する場合、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 居住継続要件: 相続開始の直前から、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月後)まで、その家に継続して住んでいること。
- 保有継続要件: その土地を、相続税の申告期限まで所有し続けていること。
つまり、相続後すぐに家を売却したり、引っ越したりしてしまうと、特例は適用できないため注意が必要です。
土地を取得するのが「同居していない親族」の場合(家なき子特例)
「親は一人暮らしで、自分は別の場所で暮らしていた」というケースで、同居していない親族が実家を相続する場合にも、一定の条件を満たせば特例が適用できます。
持ち家がない親族が親の家を相続する際に適用される可能性があることから、通称「家なき子特例」と呼ばれています。ただし、要件は非常に厳格で、以下のすべてを満たす必要があります。
- 被相続人の状況: 被相続人に配偶者がいないこと。また、相続開始時に同居していた親族もいないこと。
- 相続人の状況(居住歴): 相続開始前の3年以内に、自分や配偶者、3親等内の親族などが所有する家に住んだことがないこと。(つまり、賃貸暮らしであることなどが求められます)
- 相続人の状況(持ち家): 相続開始時に住んでいる家を、過去に一度も所有したことがないこと。
- 相続後の状況: 相続した土地を、相続税の申告期限まで所有し続けていること。
- 国籍等: 日本国籍を有していることなど、一定の条件を満たすこと。
このように、「家なき子特例」は誰でも使えるわけではなく、かなり限定的なケースを想定しています。ご自身が対象になるかどうかは、専門家を交えて慎重に判断する必要があります。
②事業用の敷地(特定事業用宅地等)
亡くなった方が個人で事業を営んでいた土地(お店の敷地など)を相続する場合に適用できるのが「特定事業用宅地等」です。
この特例を受けるには、相続人がその事業を引き継ぐことが大前提となります。
- 事業承継要件: 相続税の申告期限までに事業を引き継ぎ、その事業を継続していること。
- 保有継続要件: その土地を相続税の申告期限まで所有していること。
事業を継ぐ意思がない場合は適用できないため、注意が必要です。
③事業用の敷地(特定同族会社事業用宅地等)
亡くなった方が所有していた土地を、その親族が役員を務める同族会社(オーナー企業など)が事業のために使用していた場合に適用できるのが「特定同族会社事業用宅地等」です。
- 法人役員要件: 相続人が、相続税の申告期限において、その同族会社の役員であること。
- 保有継続要件: その土地を相続税の申告期限まで所有していること。
この特例は、中小企業の円滑な事業承継を税制面から支援する目的があります。
ただし、不動産賃貸業などは対象外となるなど、要件が細かいため、適用を検討する際は税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
④賃貸住宅等の敷地(貸付事業用宅地等)
亡くなった方がアパートやマンション、月極駐車場など、不動産貸付事業を行っていた土地を相続する場合に適用できるのが「貸付事業用宅地等」です。
- 事業承継要件: 相続税の申告期限までに貸付事業を引き継ぎ、その事業を継続していること。
- 保有継続要件: その土地を相続税の申告期限まで所有していること。
減額割合は50%と他の宅地に比べて低いですが、活用できれば大きな節税につながります。
ただし、節税目的の駆け込み対策を防ぐため、相続開始前3年以内に新たに開始した貸付事業については、原則としてこの特例の対象外となる点に注意が必要です。
特例を適用した場合の相続税シミュレーション

実際に小規模宅地等の特例を利用すると、どれくらい相続税が変わるのか、より現実的なモデルケースで比較してみましょう。
【前提条件】
- 相続した不動産: 被相続人の自宅
- 被相続人: 夫
- 相続人: 長男(同居)1名
- 相続財産:
- 自宅土地: 評価額 7,000万円 (面積250㎡)
- 自宅家屋: 評価額 1,500万円
- 預貯金: 3,000万円
- 財産合計: 1億1,500万円
- 基礎控除額: 3,000万円 + (600万円 × 1人) = 3,600万円
① 特例を利用しない場合
- 課税遺産総額 1億1,500万円 (財産合計) − 3,600万円 (基礎控除) = 7,900万円
- 相続税額 7,900万円 × 30% (税率) − 700万円 (控除額) = 1,670万円
② 特例を利用する場合
- 特例適用後の土地評価額 7,000万円 − (7,000万円 × 80%減額) = 1,400万円
- 特例適用後の財産合計 1,400万円 (土地) + 1,500万円 (家屋) + 3,000万円 (預貯金) = 5,900万円
- 課税遺産総額 5,900万円 (財産合計) − 3,600万円 (基礎控除) = 2,300万円
- 相続税額 2,300万円 × 15% (税率) − 50万円 (控除額) = 295万円
今回のシミュレーションでは、特例を適用することで相続税額が1,670万円 → 295万円 となり、1,375万円もの節税につながりました。
ただし、実際の計算は、複数の土地があったり、相続人が複数いたりすると複雑になります。正確な税額を知るためには、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
小規模宅地等の特例を利用するための手続きと必要書類

小規模宅地等の特例は、自動的に適用されるわけではありません。相続税の申告期限内(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)に、税務署へ申告書と必要書類を提出する必要があります。
相続発生から申告までの流れ
相続が始まってから申告までは、さまざまな手続きを期限内に進める必要があります。
- 死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内)
- 相続人の確定(戸籍謄本等の収集)
- 遺言書の有無の確認
- 相続財産の調査・評価
- 遺産分割協議(相続人全員で財産の分け方を話し合う)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成・提出、納税(10カ月以内)
特に、特例の適用には「遺産分割協議」がまとまっていることが原則となるため、相続人全員で協力し、計画的に進めることが重要です。期限内に協議がまとまらない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。
特例適用に必要な主な書類
申告時には、通常の相続税申告書類に加えて、特例の適用を証明するための書類を添付します。
【共通で必要な書類】
- 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
- 遺産分割協議書の写し or 遺言書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
【宅地の種類に応じて必要な書類(例)】
- 特定居住用宅地等の場合:
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の住民票の写し
- 家なき子特例を適用する場合:
- 相続人の戸籍の附票
- 賃貸借契約書の写しなど、持ち家でなかったことを証明する書類
- 貸付事業用宅地等の場合:
- 賃貸借契約書の写し
- 確定申告書の控えなど
上記はあくまで一例であり、個々の状況によって必要書類は異なります。書類に不備があると特例が認められないリスクがあるため、税理士などの専門家と連携し、確実に準備を進めることが大切です。
相続発生前に知っておきたい特例適用の4つの注意点

節税効果が非常に大きい小規模宅地等の特例ですが、適用を誤るとペナルティを受ける可能性もあります。ここでは、特に注意すべき4つのポイントを解説します。
① 遺産分割協議を申告期限までに終えること
特例を適用するには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了し、誰がどの土地を相続するかが確定している必要があります。
もし期限内に協議がまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、分割後に特例を適用できる道は残されていますが、手続きが煩雑になります。スムーズな適用のために、早めに話し合いを始めましょう。
②特例適用後の相続税が0円でも申告は必須
特例を適用した結果、課税遺産総額が基礎控除額を下回り、納める相続税が0円になったとしても、相続税の申告手続きは必ず行わなければなりません。
申告をしなければ、税務署は特例を適用する意思がないと判断し、後日、特例適用前の高額な相続税と延滞税などを請求される可能性がありす。最も陥りやすいミスの一つなので、必ず申告手続きを忘れないようにしてください。
③申告期限前の土地売却は原則NG
特例の適用要件には、多くの場合「相続税の申告期限までその土地を所有していること」が含まれています。
つまり、納税資金を確保するために、申告期限が終わる前に相続した土地を売却してしまうと、特例の対象外となってしまいます。(唯一の例外は、配偶者が自宅敷地を相続した場合)
売却によって納税額が増えるという本末転倒な事態を避けるためにも、納税資金の準備は生前から計画的に行っておくことが重要です。
④相続時精算課税制度で贈与された土地は対象外
生前贈与の一つの方法である「相続時精算課税制度」を利用して贈与された土地は、相続財産に合算して相続税を計算しますが、小規模宅地等の特例を適用することはできません。
どちらの制度を利用する方が有利になるかは、財産の状況によって異なります。生前贈与を検討する際は、この点も踏まえて総合的に判断する必要があります。
よくある質問(Q&A)

小規模宅地等の特例に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 被相続人が老人ホームに入居していた場合、空き家になった実家は特例の対象になりますか?
A1. 一定の要件を満たせば対象となります。
亡くなる直前に老人ホームなどに入居していたため、実家が空き家になっていた場合でも、以下の要件を満たせば「被相続人が居住していた」ものとして扱われ、特例を適用できる可能性があります。
- 被相続人が要介護認定や要支援認定を受けていたこと。
- 特別養護老人ホームや有料老人ホームなど、法律で定められた施設に入居していたこと。
- 実家を他人に貸したり、他の家族が住んだりしていなかったこと。
介護を理由に自宅を離れた場合でも、すぐに諦める必要はありません。
Q2. 別居していても「生計を一にしている」と認められますか?
A2. 認められるケースがあります。
「生計を一にする」とは、必ずしも同じ家で生活していること(同居)を意味するわけではありません。国税庁の通達でも、経済的なつながりの実態で判断することが示されています。
別居している場合
勤務や修学、療養などのやむを得ない理由で別居していても、以下のいずれかに該当する場合は「生計を一にする」と認められます。
- 休暇の際に帰省している
仕事や学校が休みの時には実家に戻り、一緒に生活するのが常態となっている場合。 - 常に金銭的な援助がある
生活費や学費、医療費などの仕送りが常に親族間で行われている場合。
具体的な例
- 地方の大学に進学し一人暮らしをしている子供に、親が学費や家賃、生活費を仕送りしている。
- 夫が単身赴任中で、残された家族に常に生活費を送金しており、休暇には帰省している。
同居している場合
親族が同じ家で暮らしている場合は、原則として「生計を一にする」と見なされます。
ただし、例外として「明らかに互いに独立した生活を営んでいる」と客観的に認められる場合は、生計が別だと判断されます。
独立していると見なされる例
- 二世帯住宅で玄関やキッチン、水道などが完全に分離されており、光熱費や食費もそれぞれが支払い、親子間での経済的な援助が一切ない。
上記のように、物理的な距離ではなく、家計が一つと見なせるかという実質的な観点で判断されるのがポイントです。
Q3. 二世帯住宅の場合、特例は適用できますか?
A3. 建物の登記状況によります。
二世帯住宅で特例が適用できるかのポイントは、建物の登記が「区分登記」されていないことです。
- 適用できるケース: 親子の共有名義、または親の単独名義で一つの建物として登記されている場合。この場合は、子が同居親族と見なされます。
- 適用できないケース: 親世帯と子世帯がそれぞれ独立した住戸として「区分登記」されている場合。この場合、子は同居しているとは見なされず、子の住宅部分には小規模宅地等の特例は適用されません。
家の構造ではなく、法的な登記の状態が重要になります。
まとめ|相続対策は「節税」の先を見据えることが成功のカギ
小規模宅地等の特例について、その仕組みから具体的な要件、手続き、注意点までを網羅的に解説してきました。
【この記事のポイント】
- 小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額を最大80%減額できる強力な節税制度。
- 適用には「居住用」「事業用」「貸付用」などの種類ごとに、相続人の状況に応じた複雑な要件がある。
- 特に「家なき子特例」は要件が厳しく、生前からの準備や確認が不可欠。
- 相続税が0円になる場合でも申告は必須であり、申告前の売却は原則NGなど、注意すべき点が多い。
特例を最大限に活用するには、ご自身の状況が要件に合致しているかを正確に把握し、未来を見据えて計画を立てることが何よりも重要です。
しかし、法律や税制は頻繁に改正され、要件の判断は専門家でなければ難しいのが実情です。「自分は対象になるだろう」という自己判断は、思わぬ課税リスクを招く可能性があります。
相続の成功は、その後の資産活用まで考えてこそ
相続税を無事に納め、特例を適用して節税できたとしても、それで終わりではありません。大切なのは、相続した不動産をその後どのように活用していくかです。
- そのまま住み続けるのか?
- 賃貸に出して収益を得るのか?
- より良い資産に組み替えるために売却するのか?
「相続後の運用」まで見据えて対策を立てることで、初めて「成功した相続」と言えます。
私たち未来の財託は、相続に関する深い専門知識を持つ不動産会社として、お客様1人ひとりの状況に寄り添い、最適な相続プランをご提案します。
税理士や司法書士などの専門家ネットワークを活かし、小規模宅地等の特例を適用するための生前対策から、相続発生後の複雑な手続き、そして相続した不動産の最適な活用・運用・売却のご提案まで、すべてをワンストップでサポートします。
「何から始めればいいかわからない」「うちの場合は特例が使えるのだろうか?」
そんな漠然としたご不安でも構いません。まずは一度、未来の財託の無料相談をご利用ください。お客様の大切な資産とご家族の未来を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

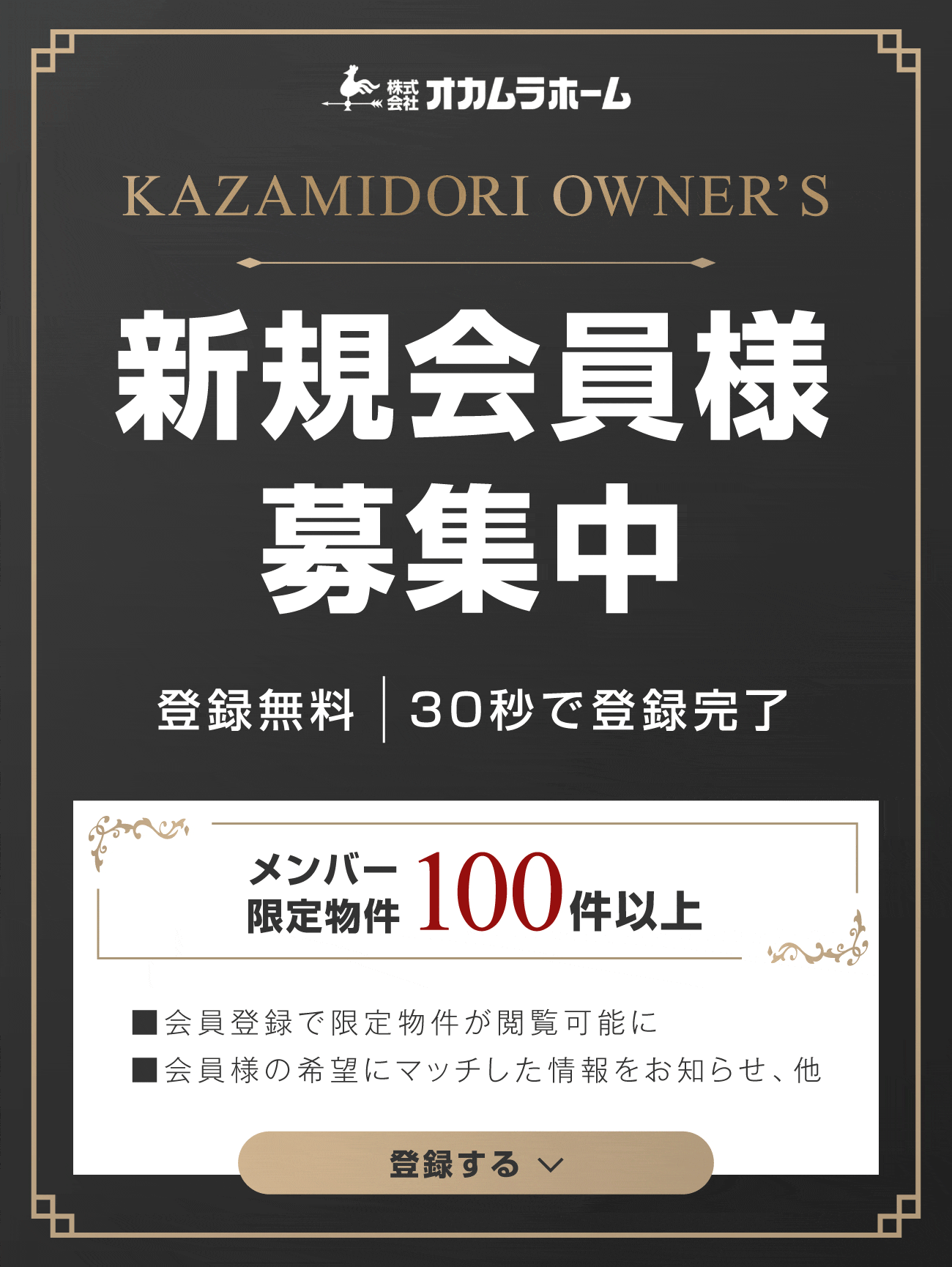

 0120-210-341
0120-210-341
