土地を貸すときの地代(借地料)相場はいくら?借地権ごとの目安や計算方法を紹介
2025.07.30
2026.01.28
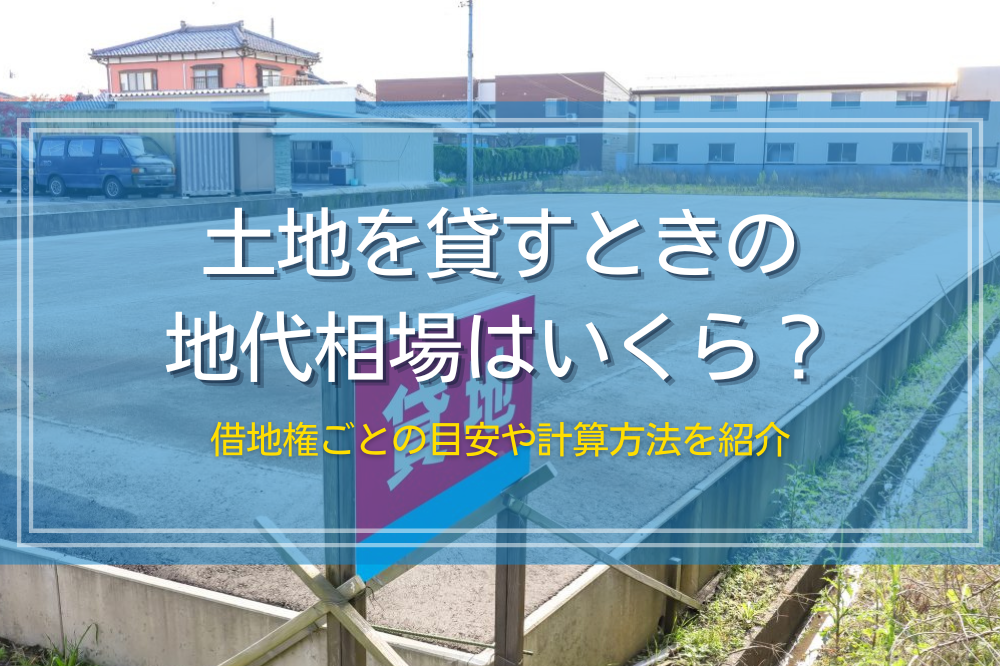
土地は所有しているだけでは税金や維持管理費がかかり続けるのみですが、「貸す」という活用方法で、安定収入を得ながら節税も期待できるなどのメリットを得られます。
このコラムでは、土地を貸すメリットや、借地権の種類、地代(借地料)の相場と計算方法について解説します。
土地を相続した方や、これから相続する予定の方は、資産を最大限に活用するための参考にしてください。
コラムのポイント
- 土地を貸すときの借地権設定の種類は「普通借地権」「一般定期借地権」「事業用定期借地権」などがあり、それぞれに地代相場が異なります。
- 地代はさまざまな要素で相場が変動するため、土地を貸したい場合は地域の不動産情報に詳しい専門家に相談するのがおすすめです。
土地を貸すメリット

土地は所有しているだけでは税金や維持管理費がかかるだけですが、貸し出すことで以下のようなメリットが得られます。
低リスクで安定収入を得られる
土地をそのまま貸し出すことで、建物を建てるなどの初期費用をかけずに長期間にわたって安定した地代収入を得られます。
節税効果が得られる
土地を貸すことで、固定資産税や相続税の節税につながる可能性があります。
例えば、建物が建っている土地は更地に比べて固定資産税評価額が6分の1または3分の1に軽減されます。
また、借地の相続税評価額の計算では借地権割合に応じた額が差し引かれるため、評価額を大きく下げることで節税が可能です。
管理の負担が少ない
土地だけを貸す場合、借主が建物を管理するため、管理コストを負担せずに賃料収入が得られる点もメリットです。
借地権の種類と貸主側のメリット・デメリット

土地を貸すときの借地契約方式(借地権)の種類は、主に以下の4つがあります。それぞれの特徴と、貸主側のメリット・デメリットを紹介します。
普通借地権
借地期間が30年以上または定めのない借地契約によって設定される借地権です。契約更新すれば借主は半永久的に土地を利用できます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
一般定期借地権
借地期間を50年以上とする借地権で、基本的に更新はなく、借主は契約終了後に土地を更地にして返還する必要があります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
事業用定期借地権
定期借地権のうち、店舗や商業施設など事業用での活用を目的としたもので、借地期間は10年以上50年未満で設定できます。一般定期借地権同様に、借主は契約終了後に土地を更地にして返還する必要があります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
建物譲渡特約付借地権
借地期間を30年以上とし、契約期間満了時に貸主が建物を買い取る特約が付いた借地権です。貸主が建物を買い取った時点で借地権は消滅します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
普通借地権は借主の権利が強く、契約終了が難しいため、最終的に土地を手放すことを考えていない場合は、定期借地権での契約を選択するのがおすすめです。
また、一般定期借地権や事業用定期借地権は、契約終了後に更地にして土地を返してもらえるため、解体費用を負担する必要がないというメリットもあります。
〈関連コラム〉
定期借地権のメリット・デメリットとは?種類別にわかりやすく解説
事業用定期借地権とは?貸主のメリット・デメリットやトラブル対策を解説
借地権の種類別地代(借地料)相場

借地権の種類ごとに、土地を貸すときの地代の相場を紹介します。
普通借地権:土地価格の1%未満+権利金
普通借地権の地代相場は、住宅利用の場合で土地の固定資産税額の3倍程度、商業利用の場合は5倍程度で、「土地価格の1%未満」とかなり安く設定されることが多くなります。
ただし、普通借地権契約では、借主は借地権設定の対価として地主に権利金を支払うのが一般的です。
権利金は、土地の更地価額に地域ごとの借地権割合(30%~90%)を掛けた金額が相場になります。
一般定期借地権:土地価格(時価)の2~3%
一般定期借地権の地代は、土地価格(時価)の2~3%が相場です。
一般定期借地権は主に借主が住宅に利用するもので、借主の利益が事業者に比べて低いことから、事業用定期借地権より地代相場は低めになります。
事業用定期借地権:土地価格(時価)の4~5%
事業用定期借地権の地代は土地価格(時価)の4~5%が相場で、「相続税路線価の6%」が目安とされています。
事業用定期借地権では、契約時に借主が地主へ「保証金」を支払うケースがあります。保証金は、契約終了時に借主へ返還される預り金のような性質で、一般的には地代の6か月分程度が相場とされています。
建物譲渡特約付借地権:土地価格(時価)の2%程度
建物譲渡特約付借地権の地代は土地価格の2%程度が相場です。
建物譲渡特約付借地権は、契約期間満了時に建物を買い取らなければならず、地主にとってメリットが少ないため、利用するケースはほとんどないと考えてよいでしょう。
また、地代相場は土地だけを貸すのか、建物を建てて貸すのかによっても変わってきます。
土地だけを貸す場合は土地の時価の0.5%~1%程度が相場とされていますが、エリアや敷地条件、需要なども考慮して決める必要があります。
具体的な地代相場は、不動産ポータルサイトや不動産会社の情報も参考にするのがおすすめです。
地代(借地料)相場の算出方法

地代の相場の根拠として用いられる計算方法は、主に以下の5パターンがあります。
- 公租公課法
- 路線価法
- 積算法
- 賃貸事例比較法
- 収益分析法
それぞれの算出方法の概要と、適用に適したケースを簡単にまとめますので参考にしてください。
公租公課法
固定資産税と都市計画税の税額(公租公課)を基準に、3~5倍の倍率を掛けて地代を計算する方法です。
固定資産税と都市計画税の税額が正確に把握できる場合や、近隣地域の類似の土地での倍率が参考になる場合などに適しています。
路線価法
路線価を基に更地価格を算出し、その1.5~3%程度を地代とする方法です。
路線価は隣接する道路の数によって計算方法が異なり、国によって補正率や影響加算率が調整される場合もあるため、地域の特性を反映した地代相場を知りたい場合に適しています。
積算法
地価に期待利回りを掛けた金額に、固定資産税や都市計画税などの諸経費を加えて地代を算出する方法です。
地域の地代相場の事例が少ない場合や、土地の期待利回りが明確な場合などに適しています。
賃貸事例比較法
周辺の類似した土地の借地料事例を基に地代を算出する方法です。
エリアの類似事例が豊富な場合や、地域の特性が統一されている都市部などで効果的な算出方法です。
収益分析法
土地の活用方法を想定し、得られる収益を予測・分析した上で地代を計算する方法です。
商業用地や事業用地で収益データが豊富な場合や、収益性を重視したい場合に適しています。周辺の収益不動産の利回り情報の収集や分析などは個人では難しいことも多いため、プロである不動産会社に相談するのがおすすめです。
まとめ
土地を貸すときの地代(借地料)の相場や計算方法をご紹介してきました。
地代は実際にはさまざまな要素で相場が変動するため、まずは地域の不動産情報に詳しい専門家に相談するのがおすすめです。
また、土地をそのまま貸すことで初期費用を抑えつつ収益を得られますが、地域の特性や状況によっては、賃貸経営や駐車場経営などの方法で活用した方が、収益性が高くなる場合もあります。
未来の財託では、借地権設定による土地の賃貸から、アパート、商業施設などの収益物件経営まで、さまざまな土地活用の中から最適な方法をご提案し、安定収入が得られるようにサポートします。
相続で土地を所有した方や、これから相続する予定の方のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

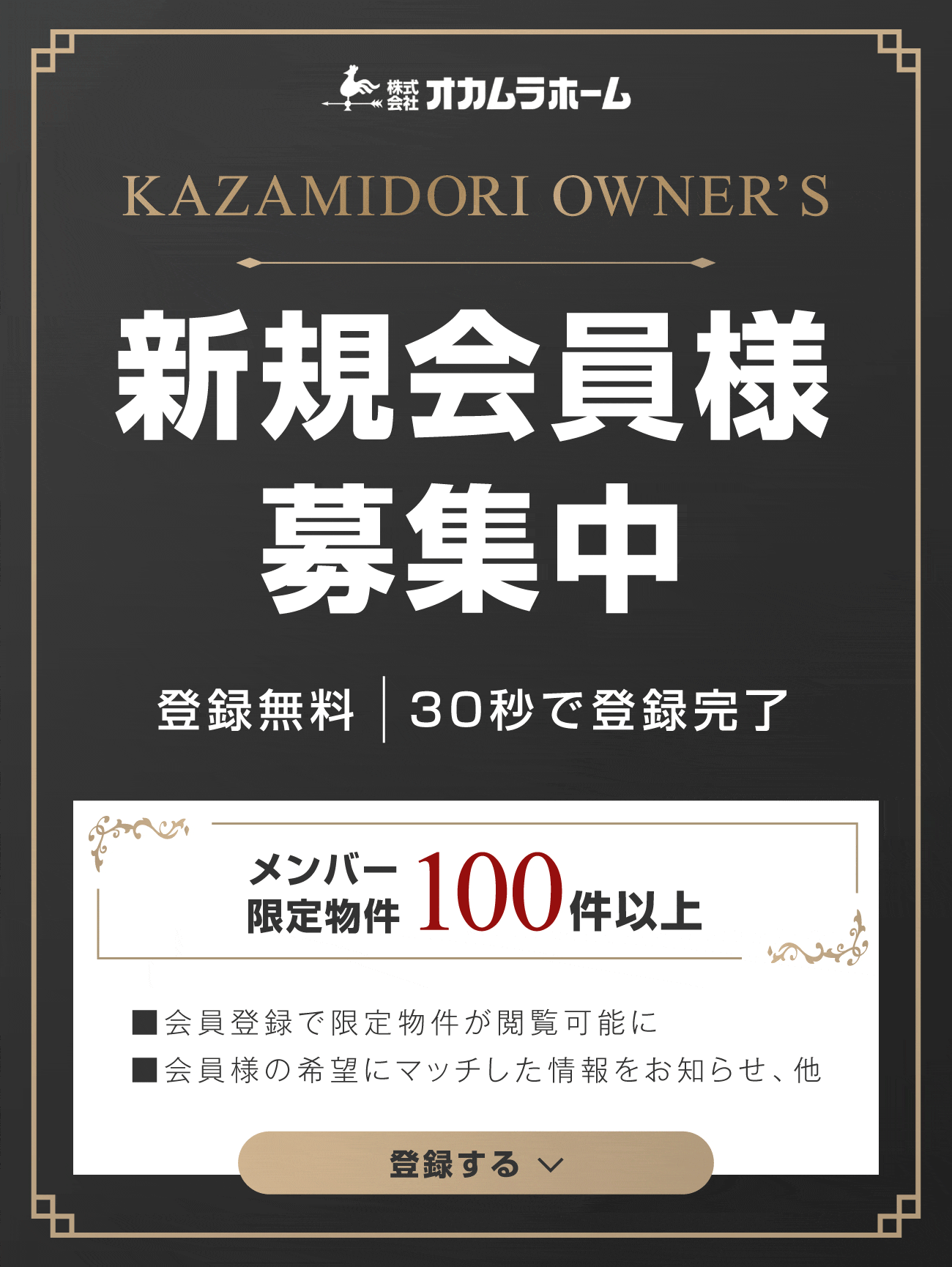

 0120-210-341
0120-210-341
