共有名義の不動産を売却する方法|相続や離婚時のトラブル対処法も解説
2025.05.15
2026.01.28
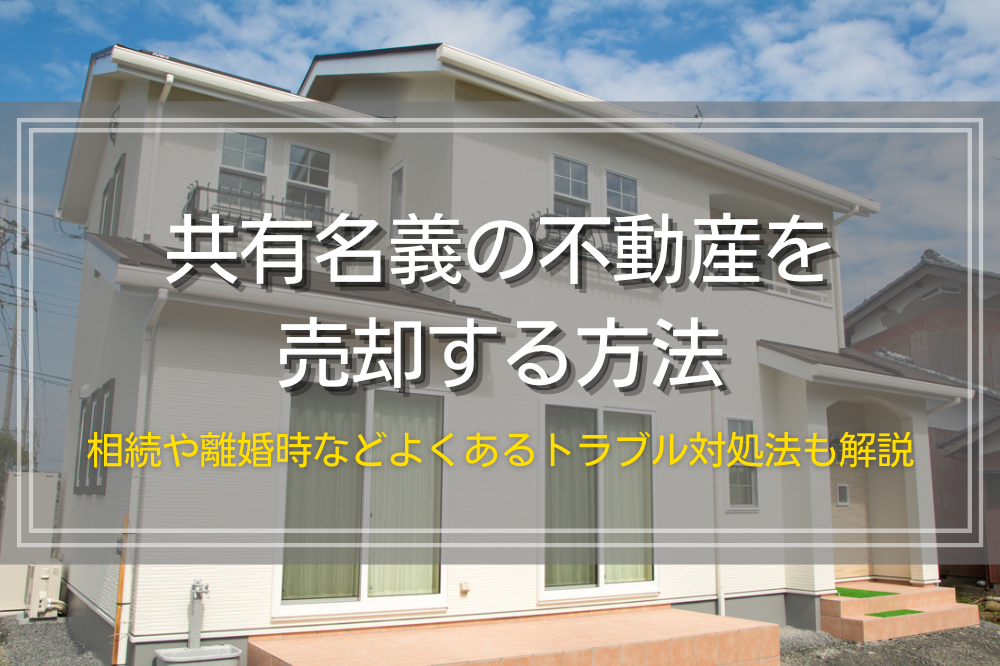
共有名義の土地や建物などの不動産の売却は、トラブルが生じやすいため注意が必要です。
このコラムでは、共有名義の不動産をお持ちの方へ向けて、スムーズな売却方法やよくあるトラブル事例と対処方法について解説します。
相続時に共有名義になってしまった不動産や、夫婦の共有名義で購入したマイホームの売却について知りたい方は参考にしてください。
コラムのポイント
- 共有名義の不動産の売却は、通常の不動産売却よりも難易度が高く、手続きも複雑になる場合があります。
- 他の共有者とのトラブルも起こりやすいため、できるだけ共有名義での不動産取得や相続を避けるのがベストです。
- すでに共有状態になっている不動産をスムーズに売却する場合は、不動産会社や弁護士、司法書士などの専門家へ相談しアドバイスを受けることをおすすめします。
共有名義の不動産とは

不動産の共有名義とは、2人以上の複数で土地や建物を共有している状態を指します。
共有名義の不動産のうち、共有者1人ひとりの持つ権利の割合のことを「共有持分」と言います。
〈関連コラム〉
不動産を共有名義で相続するメリット・デメリット|共有名義以外の相続方法や共有状態を解消する方法も解説
分割できない土地を相続するポイント|共有・分筆のリスクやスムーズに売却・活用するための対策を解説
不動産が共有名義になるのはどんなとき?
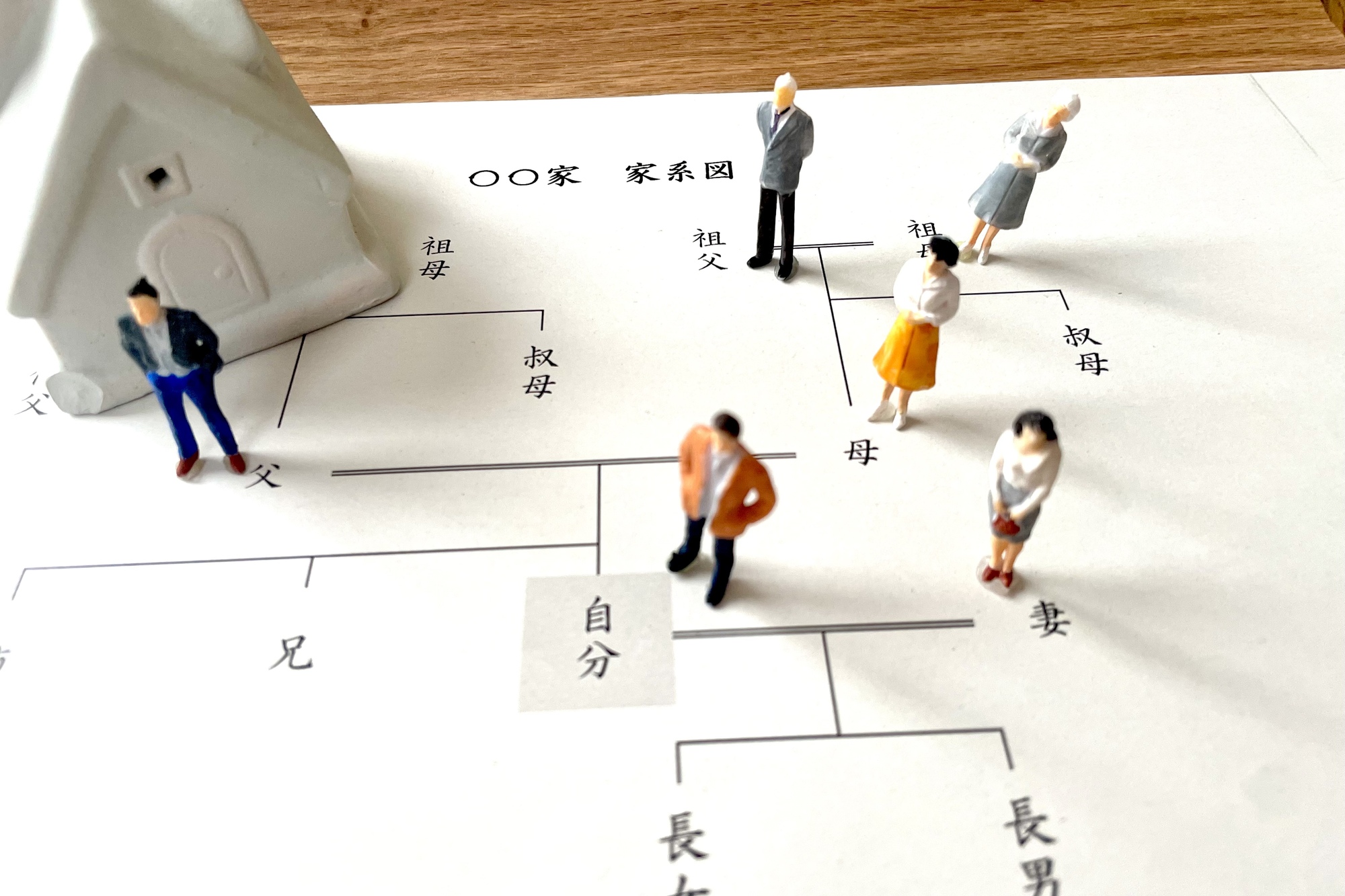
不動産が共有名義状態になるのは、主に以下のようなケースが考えられます。
①不動産を複数の相続人で相続した場合
不動産を2人以上の相続人で相続した場合、それぞれの持分による共有名義になります。
例えば、子どもが2人いる夫婦で、父親が亡くなった場合、法定相続人は配偶者である母と2人の子どもの3人になります。
3人で法定相続分に応じて土地を相続する場合、土地は母が1/2、2人の子がそれぞれ1/4の持分での共有名義になります。
②夫婦で1つの不動産を共有する場合
夫婦で費用を出し合ったり、ペアローンや連帯債務で住宅ローンを組んだりして購入したマイホームは、夫婦の共有名義になります。
例えば、4,000万円の一戸建てを夫婦でそれぞれ2,000万円ずつローンを組んで購入した場合、それぞれ1/2ずつの所有持分での共有名義となります。
共有名義の不動産を売却する方法

共有名義の不動産を売却する方法は主に以下の5パターンがあります。
- ①共有名義の不動産全体を売却する
- ②第三者に共有持分だけを売却する
- ③他の共有者への共有持分の売却・贈与
- ④共有持分を放棄する
- ⑤分筆して売却する(共有名義不動産が土地の場合)
それぞれの方法について具体的に解説していきますね。
①共有名義の不動産全体を売却する
不動産を所有している共有者全員の同意があれば、自身の持分に関係なく通常の不動産と同様に売却できます。
売却益は、各共有者の共有持分に応じて分配するのが一般的です。
不動産全体を売却できれば、共有者全員が持分割合に対して平等に現金を得られ、トラブルが起こりにくくなります。
また、不動産全体を売却すれば、通常の不動産とほぼ同じ価格で売却できる可能性が高いため、共有者全員の同意が得られる場合には最善の方法と言えます。
ただし、共有名義不動産の共有者が1人でも売却に反対していると売却できない点がデメリットになります。
②第三者に共有持分だけを売却する
自分の共有持分だけを他の共有者以外の第三者に売却する方法です。
他の共有者の同意なしで手放せるのがメリットですが、共有持分を単体で購入しても活用が難しいことや、他の共有者とのトラブルリスクが高いことから、売却価格も下がる傾向にある点にも注意が必要です。
また、売却先も、専門業者や投資家などに限られるケースが多くなります。
③他の共有者への共有持分の売却・贈与
共有持分は、他の共有者との間で譲渡契約または贈与契約を結ぶことで手放すことが可能です。
ただし、持分の譲渡・贈与には双方の合意が必要です。譲渡の場合、買い取る側には資金が必要になります。
また、贈与の場合、受け取った側に贈与税がかかる場合があるため注意が必要です。
〈暦年課税における贈与税の計算式〉
贈与税額=(共有持分の相続税評価額-基礎控除110万円)×贈与税率-控除額
例えば、共有持分の相続税評価額が600万円の場合(一般贈与財産)、贈与税は以下のようになります。
〈贈与税の計算例〉
(600万円-110万円)×30%※-65万円※=贈与税額82万円
※基礎控除後の課税価格に応じた税率と控除額を適用
譲渡(売却)する場合も、共有持分の売買価格によっては購入者に贈与税がかかることがあります。
例えば、他の共有者に共有持分25%を10%分の金額で譲渡(売却)した場合、差額の15%分の金額が実質的な贈与とみなされ、贈与税の対象になる可能性があります。
④共有持分を放棄する
共有持分を放棄して、他の共有者に持分を帰属させる方法もあります。
放棄は持分のみを売却する場合と同様に、他の共有者の同意なしで手続きを進められます。
共有名義不動産の共有持分を放棄した時は、他の共有者の共有持分割合に応じて放棄分が帰属するのが原則です。
共有持分を放棄する場合、贈与のように譲渡する相手を自由に選べないのが特徴です。
例えば、共有持分割合が3人で1/3ずつの場合、放棄する1/3を2人が分け合い、最終的に1/2ずつの共有持分割合になります。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の1人が、その持分を放棄した時、または死亡して相続人がない時は、その持分は、他の共有者に帰属する。
また、共有持分を放棄すると、受贈者となる残りの共有者には取得した分の贈与税の納税義務が課せられるため、事前に他の共有者へ放棄することを伝えた上で手続きするのがおすすめです。
⑤分筆して売却する(共有名義不動産が土地の場合)

共有名義の不動産が土地の場合は、共有者全員の同意のもと「分筆」することによって、それぞれの名義人の意思だけで売却できるようになります。
分筆とは、1つの土地を複数に分割して登記し、共有名義から単独名義にする手続きのことで、共有持分割合に応じて土地を分けるのが一般的です。
同じ不動産における共有状態が解除されるため、共有状態のデメリット(活用が難しい、売却のしにくさ)が緩和される可能性があります。
ただし、分筆後の土地の形状によっては資産価値が下がるケースもあるため、事前によく検討する必要があります。
共有名義の不動産でよくあるトラブルと対処法

共有状態の不動産を所有していることや、全体または自身の持分を売却する時に起こりやすいトラブルと対処法を解説します。
共有者の意見がまとまらず売却できない
共有状態の不動産は、売却や活用したい場合に全員の合意が得られにくく、トラブルに発展してしまったり、話し合いの期間が長期化してしまったりするケースが多くあります。
対処法:不動産会社や弁護士などの専門家に相談する
共有不動産の売却について共有者全員で合意形成するためには、各共有者と丁寧に話し合い、売却の必要性やメリットを詳しく説明し理解を得る必要があります。
共有者間での話し合いがスムーズに進まない場合には、不動産会社や弁護士などの専門家に相談し、客観的な立場からのアドバイスや仲介を依頼することも有効です。
専門家に相談することで、共有者間の信頼関係を維持しながら、全員が納得できる解決策を見つけやすくなります。
共有者が多い、連絡が取れない
共有不動産の共有者が多数いる場合、まず共有名義者を特定し、連絡先を調べ、反対する人がいないことを確認しなければなりません。
共有者が多いと、手続きのための書類準備などにも手間や労力がかかります。
対処法:司法書士のサポートを受ける
相続不動産など共有者が多い場合の売却手続きを進める方法として、司法書士にサポートを依頼する方法があります。
相続人全員が売却に同意する見込みがあれば、司法書士に依頼することで必要書類の準備や相続人への連絡などを代行してくれます。
ただし、司法書士へは相続人との交渉は依頼できません。
共有者の中に合意形成が難しい人がいる場合、司法書士に依頼したとしても売却手続きが進まない可能性があるため注意が必要です。
離婚時のトラブル
共有名義の家を持つ夫婦が離婚する場合、1人が売却して現金で分けたい、もう1人は住み続けたいという場合などにトラブルになることがあります。
家は財産分与の対象であり、財産分与の割合は基本的に2分の1ずつとされています。
例えば、登記上の持分の割合が夫70%、妻30%となっている場合でも、夫が70%を売却したなら、妻には20%分の代金を支払わなければならないことになります。
また、ペアローンや連帯債務が残っている場合、離婚時には簡単に住宅ローンをどちらか1人のローンへ一本化したり、連帯保証を解除したりすることは原則できません。
対処法:共有物分割請求を検討する
夫婦共有名義のマイホームを売却できない場合の対処法として、不動産の共有状態を解消する「共有物分割請求」の手続きをする方法があります。
共有物分割請求をすることによって、自分の共有持分について、持分割合に応じた土地やお金に変えることができるようになります。
共有物分割請求は、初めに当事者間で話し合いを行い、まとまれば裁判所を介すことなく解決できます。話し合いがまとまらない場合は、裁判所での調停に移行します。
調停で解決できない場合は訴訟を申し立てることもできますが、必ず申立人の希望通りの判決が出るわけではないため注意が必要です。
売却・贈与時に贈与税が発生しトラブルになる
前章で解説した通り、共有名義の不動産全体を売却する場合、持分割合と売却益の分け方が異なると、差額(基礎控除110万円以上の場合)が贈与とみなされて贈与税が発生することがあります。
不動産の売却価格によっては、売却益を持分割合より多く受け取った共有者が想定以上に税金を支払うことになる可能性があり、トラブルにつながるケースがあります。
また、共有名義の解消を共有持分の贈与や放棄で対応する場合、受贈者に贈与税が課せられるため同様に注意が必要です。
持分割合とかかる税金を事前に把握しておく
共有名義不動産の全体を売却する際は、持分割合に応じて売却益を分ければ贈与税は発生しません。
持分割合と異なる分け方をする場合は、事前に贈与税が発生する可能性やおよその税額を把握し共有した上で話し合うことで、トラブルを防げます。
放棄や贈与で共有持分を手放す場合も、贈与受贈予定者に事前に贈与税が発生することを共有しておきましょう。
共有持分を売却した時に起こりやすいトラブル
共有名義の不動産のうち、共有持分のみを売却した場合、持分の買主が新しく共有者となります。
その後、共有持分のみでは活用が難しい場合などに買主が他の共有者へ「持分を売却して欲しい」と求めることがあります。
話し合いがまとまらず、買主が共有物分割請求訴訟を起こすと、判決内容によっては、他の共有者も不動産を手放さざるを得なくなり、トラブルにつながることがあるため注意が必要です。
対処法:売却後のリスクを把握した上で手放す
共有名義不動産のうち、共有持分のみを売却する場合、購入希望者の目的を理解し、売却後にトラブルにつながるリスクがないかを確認することが重要です。
共有持分のみで活用が難しいと予想される不動産は、第三者よりも、現時点での他の共有者へ譲渡した方がトラブルリスクは少なくなります。
まとめ
共有名義の不動産の売却は、通常の不動産売却よりも難易度が高く、手続きも複雑になる場合があります。
また、他の共有者とのトラブルも起こりやすいため、できるだけ共有名義での不動産取得や相続を避けるのがベストです。
すでに共有状態になっている不動産をスムーズに売却する場合は、不動産会社や弁護士、司法書士などの専門家へ相談しアドバイスを受けることをおすすめします。
未来の財託は、共有名義不動産の売却・買取・活用などさまざまな方法についてご相談いただけます。
不動産の相続発生前に、相続後のトラブルを避けて適切に活用する対策を立てたいという場合もご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
〈関連コラム〉
不動産を共有名義で相続するメリット・デメリット|共有名義以外の相続方法や共有状態を解消する方法も解説
相続した土地や家を売った時の確定申告|自分でする流れや必要書類、申告不要なケースを解説

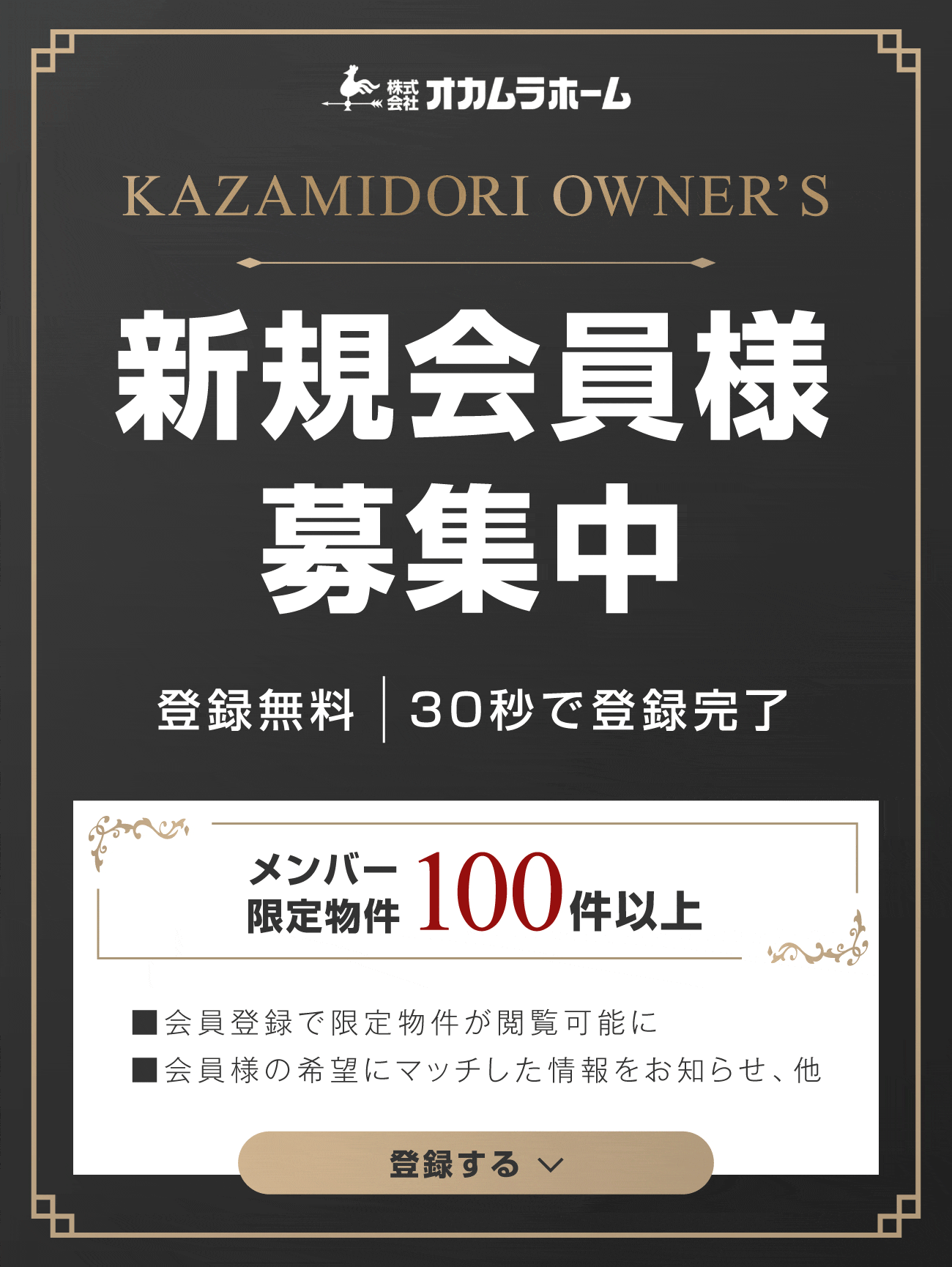

 0120-210-341
0120-210-341
