不動産を共有名義で相続するメリット・デメリット|共有名義以外の相続方法や共有状態を解消する方法も解説
2025.04.20
2026.01.28
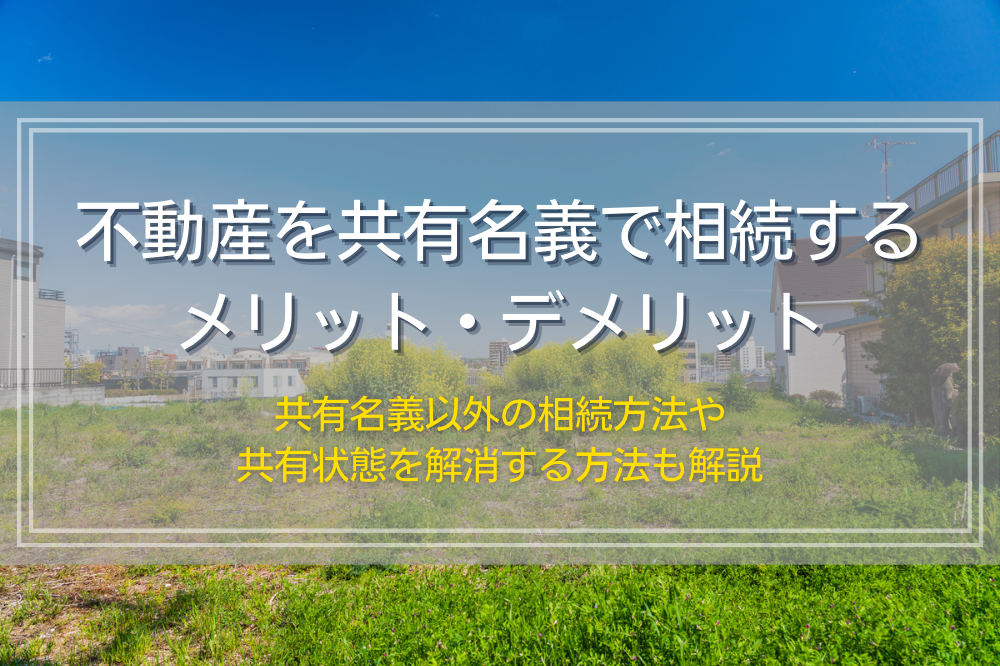
このコラムでは、土地や建物などの不動産を共有名義で相続するメリット、デメリットについて解説します。
不動産の共有を解消する方法、共有名義以外の相続方法や、相続時に共有名義になることを回避するための対策についてもご紹介しますので、相続の参考にしてください。
コラムのポイント
- 不動産を共有名義で相続すると、土地の売却・活用が難しくなったり、維持管理負担で揉めたりする可能性があるなど、さまざまなトラブルにつながりやすくなります。
- 不動産の相続を控えている場合は、共有名義での相続を避けて将来のトラブルを防ぐためにも、あらかじめ相続人同士で納得できる分割方法を決めておくのがベストです。
- 不動産を含めた相続財産をどのように分割するのが良いかはケースバイケースのため、売却・運用など複数の選択肢に詳しい専門家に相談するのがおすすめです。
不動産の共有名義とは

不動産の共有名義とは、2人以上の複数で不動産を共有している状態を指します。
相続時に不動産が共有名義になるパターンは主に、以下の2通りがあります。
- ①相続人同士の協議がまとまらなかったためやむを得ず共有名義にする
- ②相続人同士で協議の上で共有名義にする
また、①と似ていますが、遺産分割協議を行わず、相続人がそれぞれ民法による「法定相続分に応じた共有持分」を相続した際も、不動産は法定相続人の共有名義になります。
法定相続人の範囲と優先順位
- 被相続人の配偶者
- 配偶者以外で法定相続人に該当する人
第1順位:直系卑属(子ども)
※子どもが亡くなっている場合、孫・ひ孫・養子が第1順位になる
第2順位:直系尊属(父母)
※父母が亡くなっている場合、祖父母が第2順位になる
第3順位:兄弟姉妹
※兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥・姪が第3順位になる
配偶者は必ず相続人になり、それ以外は順位が上の方から優先的に相続人になります。
遺産分割における法定相続分
〈配偶者と子どもが相続人の場合〉
- 配偶者:2分の1
- 子ども(2人以上の時は全員で):2分の1
〈配偶者と直系尊属が相続人の場合〉
- 配偶者:3分の2
- 直系尊属(2人以上のときは全員で):3分の1
〈配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合〉
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で):4分の1
※子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
子どもが2人いる夫婦で、父親が亡くなった場合、法定相続人は配偶者である母と2人の子どもの3人になります。
遺産分割協議を行わず、3人で法定相続分に応じて土地を相続する場合、土地は母が2分の1、2人の子がそれぞれ4分の1の持分による共有名義になります。
不動産を共有名義で相続するメリット・デメリット

土地や建物などの不動産を共有名義で相続するメリットとデメリットを分かりやすく解説します。
メリット
共有名義での不動産相続は、各相続人が不動産の持分を公平に得られる点が最大のメリットです。
不動産を1人が相続したことによる不公平感によって、相続人から不満が出てトラブルになることを防げます。
また、遺産分割協議が進まない場合など、いったん法定相続分で共有名義の相続登記をした方が良い場合もあります。共有登記した上でしっかりと協議を行い、まとまった時点で改めて分割するという方法も取れます。
デメリット
共有者全員の同意がないと売却・活用できない
共有名義の不動産は、1つの土地として売却したり、賃貸に出したりするには、原則として共有者全員の同意が必要になる点がデメリットです。
相続人全員から同意が得られないと、賃貸化できるまでに大きなタイムラグが発生したり、手続きを進められずに土地や建物を長期間放置することになってしまったりする可能性もあります。
維持管理費用の負担割合でトラブルになる恐れがある
複数の相続人の共有名義になった不動産は、維持管理や納税も共有持分に応じて連帯して行う必要があるため、負担割合でトラブルになるケースがあります。
例えば、共有名義の不動産の固定資産税納税通知書は、共有者全員ではなく代表者1人に送付されます。代表者は固定資産税を支払った後、各共有者に建て替え分を請求することになりますが、きちんと支払いがされなければ1人にかかる負担が大きくなります。
また、代表者が固定資産税を支払わなかったために、連帯納付の義務がある他の共有者へ請求され、トラブルに発展することもあるため注意が必要です。
次世代の相続が複雑になる
複数人の共有名義になった不動産は、代替わりの度に共有者が増えることでさらに売却や活用がしづらくなってしまいます。
また、共有者が増え続けた結果、容易に所有者が特定できない「所有者不明」の不動産になると、将来的に社会的に悪影響を与える可能性もあります。
共有名義での相続を避ける方法

不動産の相続が発生した際、複数の相続人の共有名義になることを防ぐ方法を、相続発生前、発生後に分けてまとめます。
相続発生後に不動産の分割方法を決める際は、遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることが必要ですので、事前にメリット、デメリットを理解した上で話し合うことで意見をまとめやすくなります。
相続発生前にできる対策方法

被相続人が遺言書で分割方法を指定する
相続発生前にできる対策として、被相続人が遺言書で「相続人の1人に単独で不動産を引き継ぐ」と指定しておくことで、不動産の共有名義での相続を避けられ、トラブルを未然に防げます。
なお、相続人の間で不公平が生じないように、不動産を引き継がない相続人には預貯金など他の財産を相続させるよう指定することも忘れないようにしましょう。
被相続人の生前に不動産を売却する
被相続人の財産が不動産のみだった場合、遺言書で1人に不動産を引き継ぐ方法では、他の相続人は民法で最低限認められた取り分(遺留分)を取得できません。
上記の場合、不動産を生前に売却すれば遺産は現預金のみとなり、現預金を公平に分配すれば遺留分で揉める心配がなくなります。
ただし、生前に不動産を手放せる状況であることが必要な点に留意しましょう。
相続発生後の対策方法
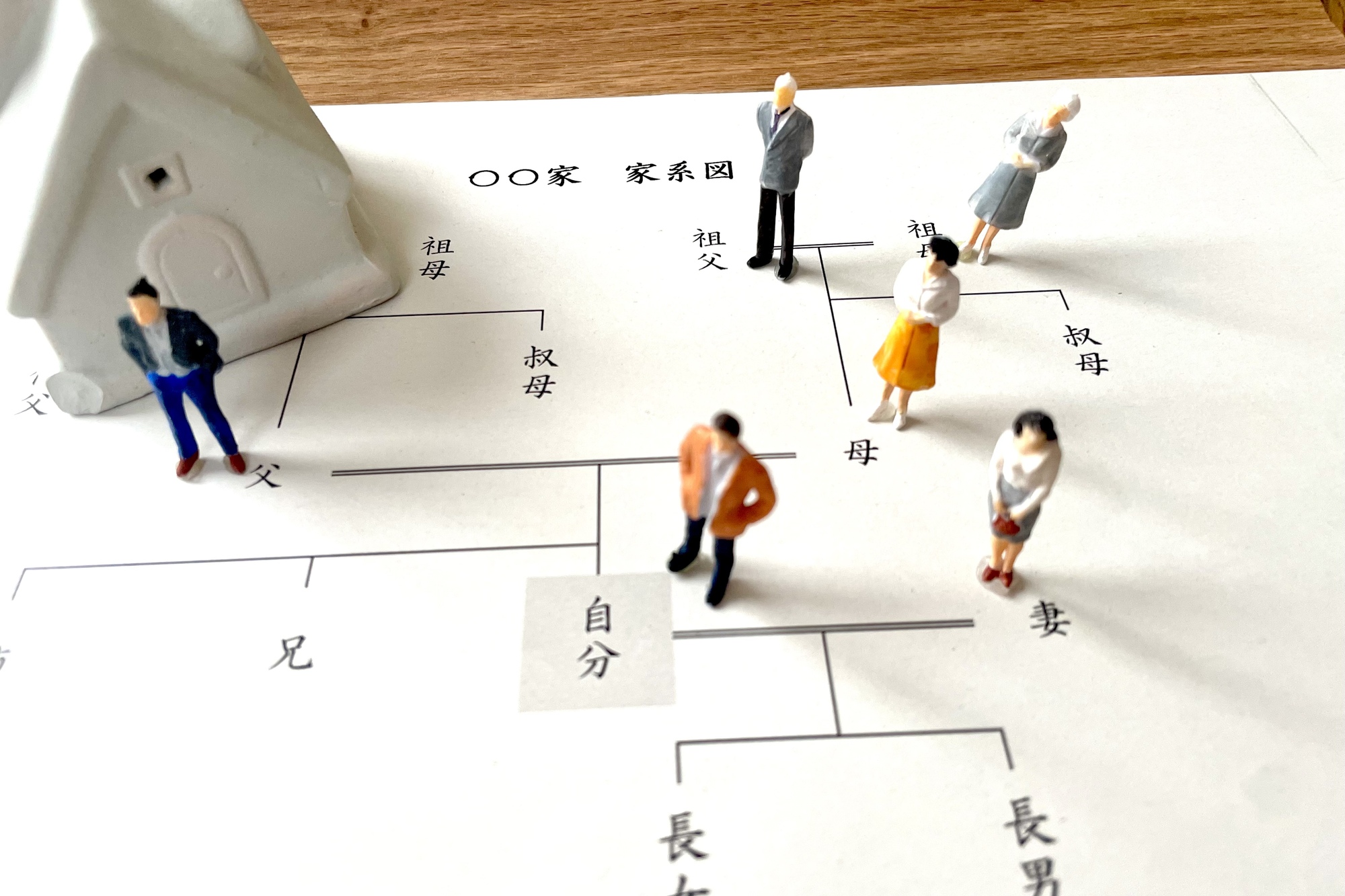
不動産を1人が相続して他の人に代償金を支払う(代償分割)
遺産分割協議の上で不動産を1人が相続し、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」であれば、不動産が複数の共有名義にならずに済みます。
例えば、相続人が3人で、1人が評価額6,000万円の不動産を相続した場合、他の2人の相続人に2,000万円ずつ代償金を支払うことで公平に分けられます。
ただし、不動産の評価額が極めて高い場合など、相続人の1人が単独で不動産を相続しても代償金を支払えない場合、代償分割は難しくなります。
不動産を売却して現金に換えて分ける(換価分割)
不動産を売却し、現金に換えて各相続人で分ける「換価分割」なら、相続人が誰も不動産を所有しないため、共有名義になることはありません。
換価分割のメリットは、代償金の負担なく公平に財産を分けられることです。
ただし、不動産を手放さなければならないため、先祖代々の土地を守っていくことを重視する場合や、売却に難色を示す相続人がいる場合は実現が難しくなります。
また、不動産を売却して得た売却益はそのまま分割できるわけではなく、仲介手数料などの諸費用や譲渡所得税等が差し引かれることにも注意が必要です。
〈関連コラム〉
相続した空き家の売却でかかる税金は?計算方法や「空き家特例」を活用した節税方法も解説
相続した不動産を売却する流れ|税金や必要書類、相続人同士での分割方法も解説
不動産を分筆登記してそれぞれが単独所有する
不動産を相続人全員で分筆登記し、それぞれが単独で所有することで、共有名義状態を避けることもできます。
ちなみに、建物が建っている土地でも分筆登記は可能です。ただし土地の所有者と建物の所有者が異なると後々トラブルを招く可能性もあります。
他にも、土地面積が小さくなり価値が低下することで売却時の利益が減ったり、活用しづらくなったりするなどリスクも大きいため、相当に広い土地でない限り、分筆せずに単独で相続することが望ましいでしょう。
不動産の共有状態を解消する方法

遺産分割協議がまとまらずに共有登記になってしまった不動産について、共有状態を解消する方法についてまとめます。
共有名義の不動産全体を売却する
共有名義の不動産全体を売却することで、共有状態を解消する方法です。売却代金を持分割合に合わせて分配すれば、公平に分割できます。
自分の共有持分だけを売却するより、共有名義の不動産全体を売却する方が高値で売却できる可能性が高いため、共有者全員の同意が得られる場合には最善の方法と言えます。
共有者間で持分を譲渡・贈与して名義人を減らす
共有名義の不動産は、共有者間で持分の譲渡契約や贈与契約を結ぶことにより、名義人を減らしたり単独所有にしたりできます。
ただし、持分を譲渡・贈与する場合は双方の合意が必要になる他、譲渡の場合は持分を買い取る側に資金が必要です。また、贈与の場合は受けた側に贈与税がかかる場合がある点も覚えておきましょう。
共有持分を第三者に売却する
共有名義の不動産のうち、自分の持分だけを第三者に売却することで、共有状態を解消できます。
自分の持分だけを売却するのであれば、他の共有者の同意は不要です。ただし、不動産全体を売却するよりも買い手が見つかりにくくなるため、場合によっては長期間売却できない可能性もあります。
共有名義の不動産を売却する場合は、相続によって発生する不動産の売買に詳しい専門知識のある不動産会社に相談するのがおすすめです。
相続放棄する
相続放棄によって不動産の共有持分を放棄することで、共有状態を解消できます。
ただし、相続放棄は共有持分以外の財産もすべて相続できなくなるため、プラスの資産が多い場合は相続放棄によるデメリットが大きくなる点に注意が必要です。
他の遺産は相続し、共有持分だけを手放したい場合は、いったん共有名義で相続した後で売却する方が良いでしょう。
〈関連コラム〉
空き家を相続放棄するメリット・デメリット|ほかの対処法も解説
まとめ
不動産を共有名義で相続すると、土地の売却・活用が難しくなったり、維持管理負担で揉めたりする可能性があるなど、さまざまなトラブルにつながりやすくなります。
不動産の相続を控えている場合は、共有名義での相続を避けて将来のトラブルを防ぐためにも、あらかじめ相続人同士で納得できる分割方法を決めておくのがベストです。
不動産を含めた相続財産をどのように分割するのが良いかはケースバイケースのため、売却・運用など複数の選択肢に詳しい専門家に相談するのがおすすめです。
未来の財託では、土地や家など各種不動産の相続手続きや売却/買取、活用、リフォーム、維持管理に関することまで、当社提携の税理士と共にさまざまなお悩みを解決するためにサポートをいたします。
千葉・東京23区エリアで不動産の相続を予定している方や、相続不動産の売却・活用を検討している方はお気軽にご相談ください。

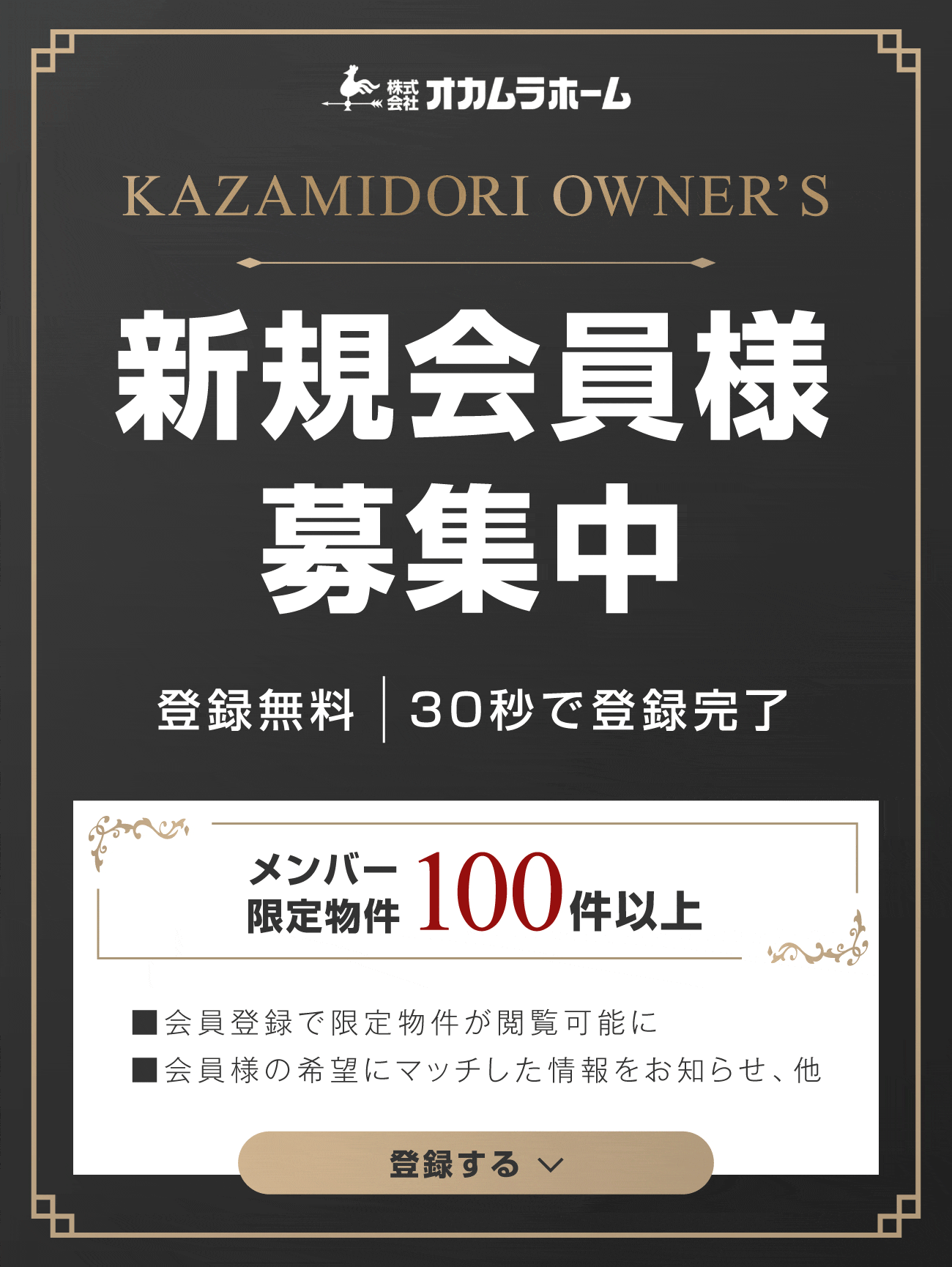

 0120-210-341
0120-210-341
