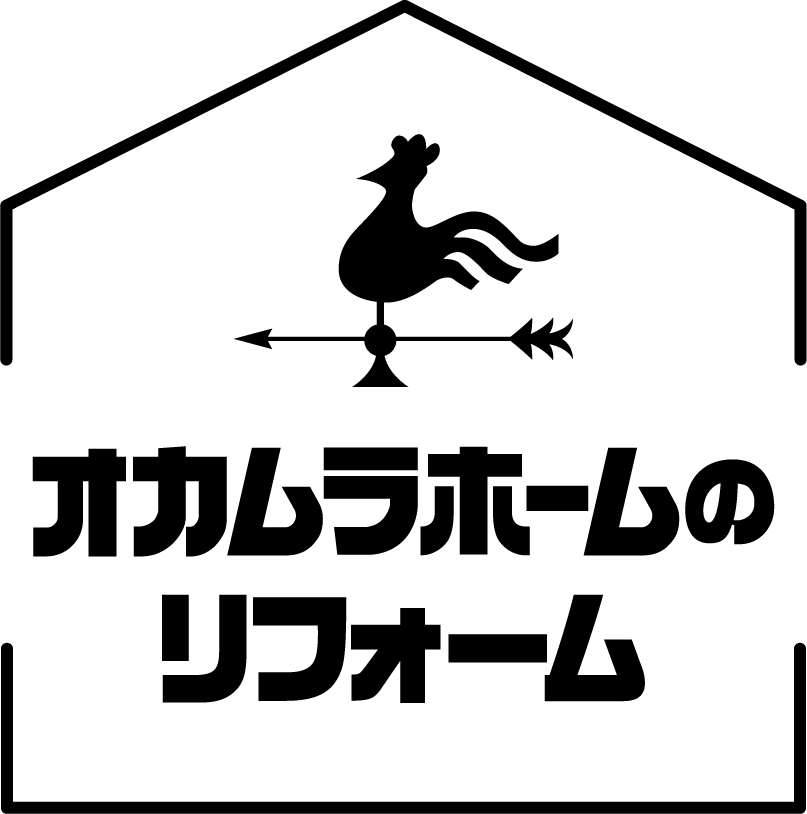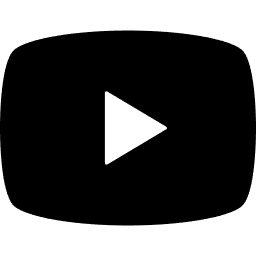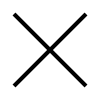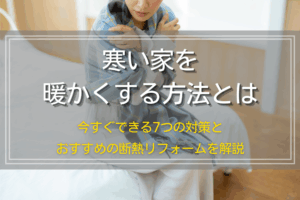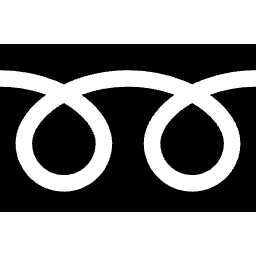【2025年最新】リフォーム減税とは|種類や条件、いつまで申請可能かわかりやすく解説
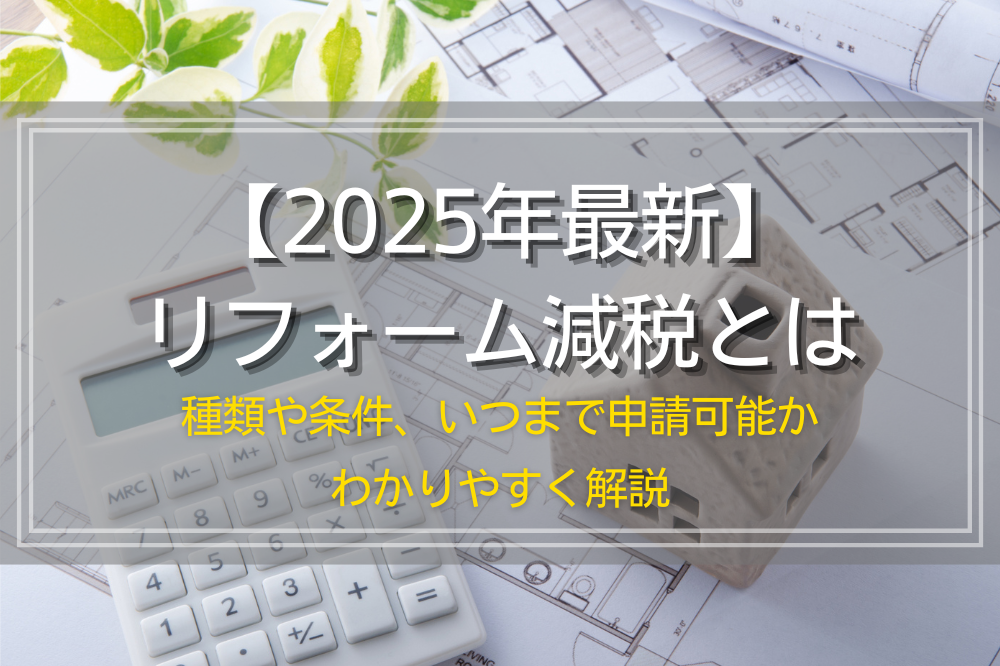
リフォームにかかる実質的負担を抑えるには、リフォーム減税を活用するのがおすすめです。
そこで本記事では、多くの住宅リフォームを手がけている千葉の工務店「オカムラホーム」が、どのようなリフォームが対象となるのか、いつまで申請できるのかなど、リフォーム減税について詳しく解説します。
Contents
リフォーム減税とは

リフォーム減税では、対象となる住宅リフォームを行った場合、所得税や固定資産税などの税負担で優遇措置を受けられます。
リフォームにかかる実質的負担を抑えられるため、改修費用を抑えたいとお悩みの場合には活用したい制度です。
大きく分けて所得税の減税と固定資産税の減税の2種類に分けられており、それぞれで対象工事や条件が異なるため、利用する際には注意しましょう。
リフォーム減税①所得税の減額

所得税の減額は、住宅ローン減税(増改築)とリフォーム促進税制の2つが用意されています。
住宅ローン減税(増改築)
住宅ローン減税は、リフォームで10年以上の住宅ローンを組んだ場合、年末時点における住宅ローン残高の0.7%が、所得税(住民税)から控除される制度です。
控除を受けられる期間は最大10年間とされています。
住宅ローン減税の対象工事
次の6種類の工事のうちいずれかに該当する場合、住宅ローン減税の対象となります。
- 増築、改築、建築基準法に規定する大規模修繕/大規模な模様替え
- マンションなど区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕/模様替え
- 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕/模様替え
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の断熱改修工事
住宅ローン減税の条件
住宅ローン減税を受けるには、以下の6つの条件を満たしている必要があります。
- リフォームを行う方が所有し、居住する家屋
- リフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上
- 対象工事に係る工事費用が100万円(税込)超
- 当該リフォームのために償還期間10年以上の住宅ローン等がある
- その年の合計所得金額が2,000万円以下
- リフォーム完了後6ヶ月以内に居住し、各年12月31日まで居住している
対象となるリフォームを行なっていても、上記6つの条件に該当しない場合、優遇措置は受けられないため注意しましょう。
リフォーム促進税制
リフォーム促進税制は、対象となる改修工事を行った場合、工事費用の10%が所得税から控除される制度です。
ローンの有無によらず、自己資金でリフォームを行なった場合に対象となります。
リフォーム促進税制における対象工事と、それぞれの最大控除額は次の通りです。
| 必須工事 | 対象工事限度額 | 控除率 | 最大控除額 | |
| 耐震 | 250万円 | 10% | 62.5万円 | |
| バリアフリー | 200万円 | 60万円 | ||
| 省エネ | 250万円(350万円※) | 62.5万円(67.5万円※) | ||
| 三世代同居 | 250万円 | 62.5万円 | ||
| 長期優良住宅化 | 耐震+省エネ+耐久性向上 | 500万円(600万円※) | 75万円(80万円※) | |
| 耐震 or 省エネ+耐久性向上 | 250万円円(350万円※) | 62.5万円(67.5万円※) | ||
| 子育て | 250万円 | 62.5万円 | ||
※()内の金額は、省エネ改修工事+太陽光発電設備を設置する場合。
<参照>住宅のリフォームに係る税の特例措置|国土交通省
また、必須工事における限度額超過分、あるいはその他の工事についても、5%の税額控除が可能です。
| 工事の種類 | 対象工事限度額 | 控除率 |
| 必須工事の対象工事限 度額超過分及びその他 のリフォーム |
1,000万から必須工事の対象工事限度額を引いた額 | 5% |
所得税減税の対象となる各リフォームに関しては、細かな適用条件が設けられています。
申請する場合には、「リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について」から詳細の資料を確認し、条件を必ず確認しましょう。
リフォーム減税②固定資産税の減額

固定資産税の減額措置は、リフォーム減税におけるリフォーム促進税制にて受けることができます。
対象となる工事を行なった住宅について、工事完了の翌年度分の固定資産税が減額されます。
対象となる住宅は、次のリフォームを行なった住宅です。
| 対象工事 | 減額される割合 |
| 耐震リフォーム | 1/2 |
| 省エネリフォーム | 1/3※1 |
| バリアフリーリフォーム | 1/3 |
| 長期優良住宅化リフォーム | 2/3※2 |
※1 耐震改修工事の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年減額
※2 2年目は1/2減額
所得税の減税と同様に、それぞれのリフォームについて細かな適用条件が設けられているため注意しましょう。
<参照>リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について|国土交通省
リフォーム減税の対象工事

リフォーム減税の対象工事は、バリアフリー化リフォームや耐震リフォームなど、住宅の機能や性能を高めるリフォームに限られています。
ここからは、具体的にどのような工事が対象となるか確認していきましょう。
耐震リフォーム
昭和56年5月31日以前に着工された住宅(旧耐震基準で建てられた住宅)を、現行の耐震基準に適合させるリフォームを行う場合、リフォーム減税の対象となります。
具体的なリフォーム例は次の通りです。
- 補強材(ブレース)の取り付け
- 耐震パネルの設置
- 柱や梁などの交換
- 屋根の軽量化
しかし、所得税の減額と固定資産税の減額では対象条件が異なり、固定資産税の減額を受ける場合は耐震改修工事費が50万円(税込)で対象となるため注意しましょう。
省エネリフォーム
住宅の断熱性・気密性を向上させ、エネルギー消費量の低い省エネ住宅にリフォームする場合も、リフォーム減税の対象となります。
具体的なリフォーム例は次の通りです。
- 内窓の設置やサッシ交換
- 高断熱なガラスへの交換
- 壁・床・天井の断熱リフォーム
- 高効率エアコンや高効率給湯器の設置
- 太陽光発電システムの設置
このうち、窓の断熱改修工事は必須工事とされているため注意しましょう。
バリアフリー化リフォーム
「要介護」や「要支援」の認定を受けている方や、ご高齢の方、障がいを持っている方の生活の利便性を上げる工事を行う場合、リフォーム減税の対象となります。
具体的なリフォーム例は次の通りです。
- 廊下の拡張
- 手すりの設置
- 段差解消
- 開き戸から引き戸への変更
- 滑りにくい床材への変更
- トイレのバリアフリー化
同居対応リフォーム
親・子・孫の三世代が同居する家にリフォームする場合も、リフォーム減税を受けられる可能性があります。
具体的なリフォーム例は次の通りです。
- キッチンの増設工事
- 浴室の増設工事
- トイレの増設工事
- 玄関の増設工事
減税制度の対象となるには、上記の増設工事を行い、キッチン・浴室・トイレ・玄関のうち2つ以上が複数設置されている必要があります。
そのため、玄関が2箇所・トイレが3箇所・キッチンと浴室はそれぞれ1箇所という場合は対象ですが、トイレが3箇所で、玄関とキッチン、浴室は1箇所ずつという場合は対象となりません。
長期優良住宅化リフォーム
長期優良住宅の認定を受けるためにリフォームを行う場合、リフォーム減税の対象となります。
具体的なリフォーム例は次の通りです。
- 小屋裏の換気性向上
- 外壁を通気構造化
- 浴室・脱衣室の防水性向上
- 床下の防湿性向上
- 土台の防腐・防蟻処理
- 地盤の防蟻処理
- 雨どいの設置
各工事によって、対象となる住宅の種類(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造)が異なるため注意しましょう。
子育て対応リフォーム
子育てしやすい環境を整備するためにリフォームを行う場合、所得税の減額のみ対象となります。
具体的なリフォーム例は次の通りです。
- お子さまの事故防止を目的とした工事
- 対面式キッチンへの交換
- 子ども部屋や収納の増設
- 開口部の防犯性・防音性向上
また、次の2つの条件も満たしている必要があります。
- お子さまのご年齢が19歳未満
- ご夫婦どちらかが40歳未満
リフォーム減税の申請方法と必要書類

リフォーム減税を利用するには、期間内に必要書類を用意して、申請を済ませる必要があります。
ここからは、リフォーム減税の申請方法と必要書類について確認していきましょう。
リフォーム減税の申請方法
リフォーム減税で所得税の減額措置を受ける場合、大まかな流れは以下の通りです。
- リフォーム業者を選定し、減税制度への適用可否を確認する
- リフォーム工事を進める
- リフォーム工事の完了後、費用を支払い、施工業者に各種証明書の発行を依頼する
- 必要書類をそろえて、地域所管の税務署に確定申告を行う
上記の通り、所得税の減額を受けるには、確定申告を行わなければなりません。
一方、固定資産税の減額措置を受ける場合は、次の流れになります。
- リフォーム業者を選定し、減税制度への適用可否を確認する
- リフォーム工事を進める
- リフォーム工事の完了後、費用を支払い、施工業者に各種証明書の発行を依頼する
- 必要書類をそろえて、自治体の担当窓口に直接申告する
固定資産税の減額措置を受ける場合は、各市区町村の担当窓口に直接申告する必要があります。
期間は工事完了後3ヶ月以内と決められているため注意しましょう。
申請に必要な書類
リフォーム減税を受けるために必要な書類は、住宅ローン減税か、あるいはリフォーム促進税制かによって異なります。
住宅ローン減税で必要となる主な書類は以下の通りです。
- 確定申告書
- 住民票の写し
- 工事請負契約書の写し
- 増改築等工事証明書
- 登記事項証明書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- ローンの年末残高証明書 など
一方、リフォーム促進税制では次の書類が必要となります。
- 確定申告書
- 工事請負契約書の写し
- 増改築等工事証明書
- 固定資産税の減額申告書
- 源泉徴収票
- 登記事項証明書
- 住宅特定改修特別税額控除の計算証明書 など
確定申告書や登記事項証明書など重複する書類もありますが、いくつか異なる点もあるため注意が必要です。
リフォーム減税の申請はいつまでか
リフォーム減税の申請期間は、減額措置を受ける税金の種類によって異なります。
所得税の場合、工事を行った年の翌年の確定申告期間中(基本的には2月16日〜3月15日)に申請が必要です。
しかし、源泉徴収によって支払ってきた税の総額が実際の所得税額より多く、還付申告を行う場合は、工事を行なった翌年の1月1日から5年間が申請期間となります。
一方、固定資産税の減額措置を申請する場合、工事完了後3ヶ月以内が申請期限です。
所得税とは異なり、確定申告期間が期限ではないため注意してください。
祖父母や両親からの援助は贈与税の非課税措置も利用可能

祖父母や両親からリフォーム資金の援助を受けた場合、リフォーム減税による所得税・固定資産税だけでなく、贈与税の非課税措置制度も活用できます。
令和8年12月31日までに贈与されたものが対象となり、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。
限度額や要件は次の通りに設定されています。
| 贈与税非課税限度額 | 質の高い住宅:1,000万円 一般住宅:500万円 |
| 要件 | 贈与を受けた年の受贈者の所得が2,000万円以下 |
| 床面積 | 50㎡以上(※) |
※ 合計所得金額が1,000万円以下の受贈者は40㎡以上50㎡未満の住宅も適用
断熱等性能等級4以上、耐震等級2以上、高齢者等配慮対策等級3以上などの要件を満たしている場合、「質の高い住宅」に該当し、1,000万円まで非課税となります。
贈与税の非課税措置を受けたい場合には、非課税措置を受ける旨を記載した贈与税の申告書を作成し、必要書類を添付して納税地の所轄税務署に提出してください。
提出期間は、贈与された翌年の2月1日〜3月15日までのため、忘れないように注意しましょう。
リフォーム減税を申請する際の注意点

リフォーム減税を利用して所得税・固定資産税の減額措置を受ける場合、次の3点に注意しましょう。
申請期限を守る
リフォーム減税によって減額措置を受けるには、申請期間中に必要書類を提出する必要があります。
注意しておきたいのが、所得税と固定資産税で申請期限が異なるということです。
所得税の場合、工事を行った年の翌年の確定申告期間までとされていますが、固定資産税は工事完了後3ヶ月以内に申請しなければなりません。
どちらも確定申告期間までだと勘違いし、申請期限を過ぎてしまわないように、スケジュール管理は慎重に行いましょう。
所得税の減額措置は確定申告必須
リフォーム減税で所得税の減額を申請するには、確定申告を必ず行わなければなりません。
自営業の方だけでなく、会社員の方であっても確定申告が必須です。
住宅ローン減税の場合、2年目以降は年末調整で処理しますが、初年度は確定申告が必要となるため注意してください。
対象条件を満たすため準備を徹底する
リフォーム減税で減額措置を受けるには、対象工事の要件を満たし、必要書類をもれなく用意する必要があります。
そのため、リフォームを計画する段階から、対象要件を考慮したプラン作りが欠かせません。
そこで重要となるのが、リフォーム会社選びです。
リフォーム実績が豊富で、減税制度にも精通した会社であれば、リフォームの計画から施工、必要書類の準備までスムーズに進みます。
対象条件外となってしまうリスクを軽減するには、リフォーム会社選びから入念に行うことをおすすめします。
まとめ
リフォーム減税を申請すれば、所得税・固定資産税の負担を抑えられるのがメリットです。
しかし、対象となる工事の要件は細かく決められているため、リフォーム会社のサポートのもと、準備を適切に進める必要があります。
耐震リフォームや省エネリフォームなど幅広いリフォームに対応しており、減税制度にも詳しいリフォーム会社に相談することで、申請までをスムーズに進めましょう。
お問い合わせ
お問い合わせいただきましたお客様には
担当者より順次対応をさせていただきます。