土地の贈与税がかからない・節税する方法|生前贈与で不動産を引き継ぐ際の注意点も解説
2025.06.15
2025.12.26
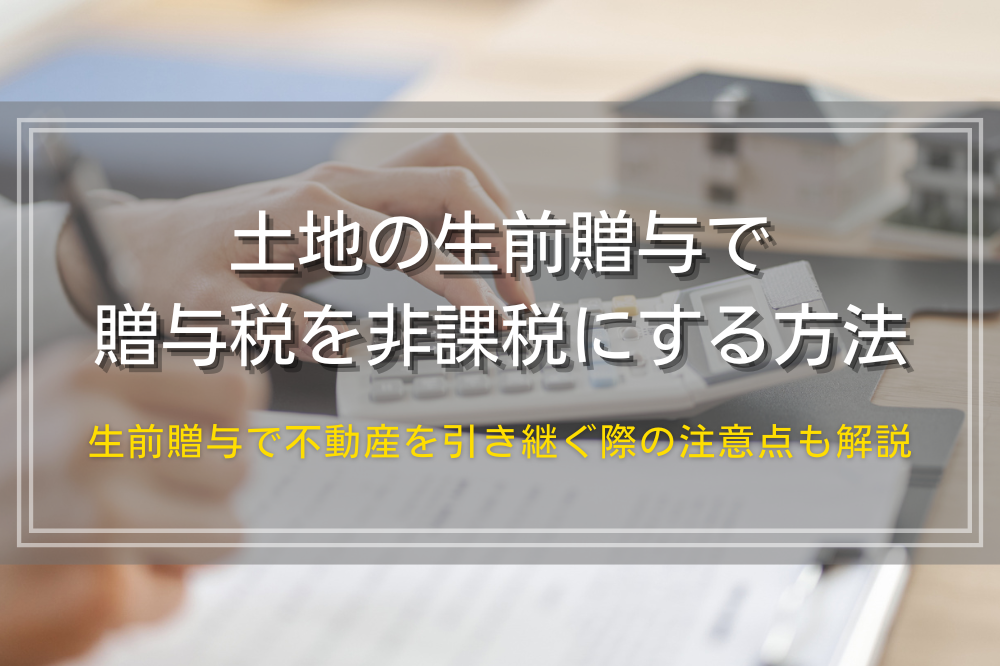
親などから土地を引き継ぐ予定がある場合、「相続前に生前贈与を受けるべきか」迷っているという方もいるのではないでしょうか。
しかし、生前贈与は土地の評価額が大きければ大きいほど、相続よりも税負担が重くなる点に注意が必要です。
このコラムでは、土地の贈与を受けた場合に贈与税がかからない、または節税できる方法を解説します。
コラムのポイント
- 評価額の高い土地を暦年課税で一度に贈与すると、贈与税が高額になる可能性があります。
- 贈与税を非課税にする、または節税する方法として「相続時精算課税制度の利用」「居住用不動産の配偶者控除の活用」「土地の持分を少しずつ贈与する方法」の3つを紹介します。
- 節税効果も考慮しつつ、適切に財産の移転を行うためには、相続対策に精通した不動産会社のアドバイスを受けるのがおすすめです。
Contents
相続予定の土地の贈与を受けるのはどんな時?
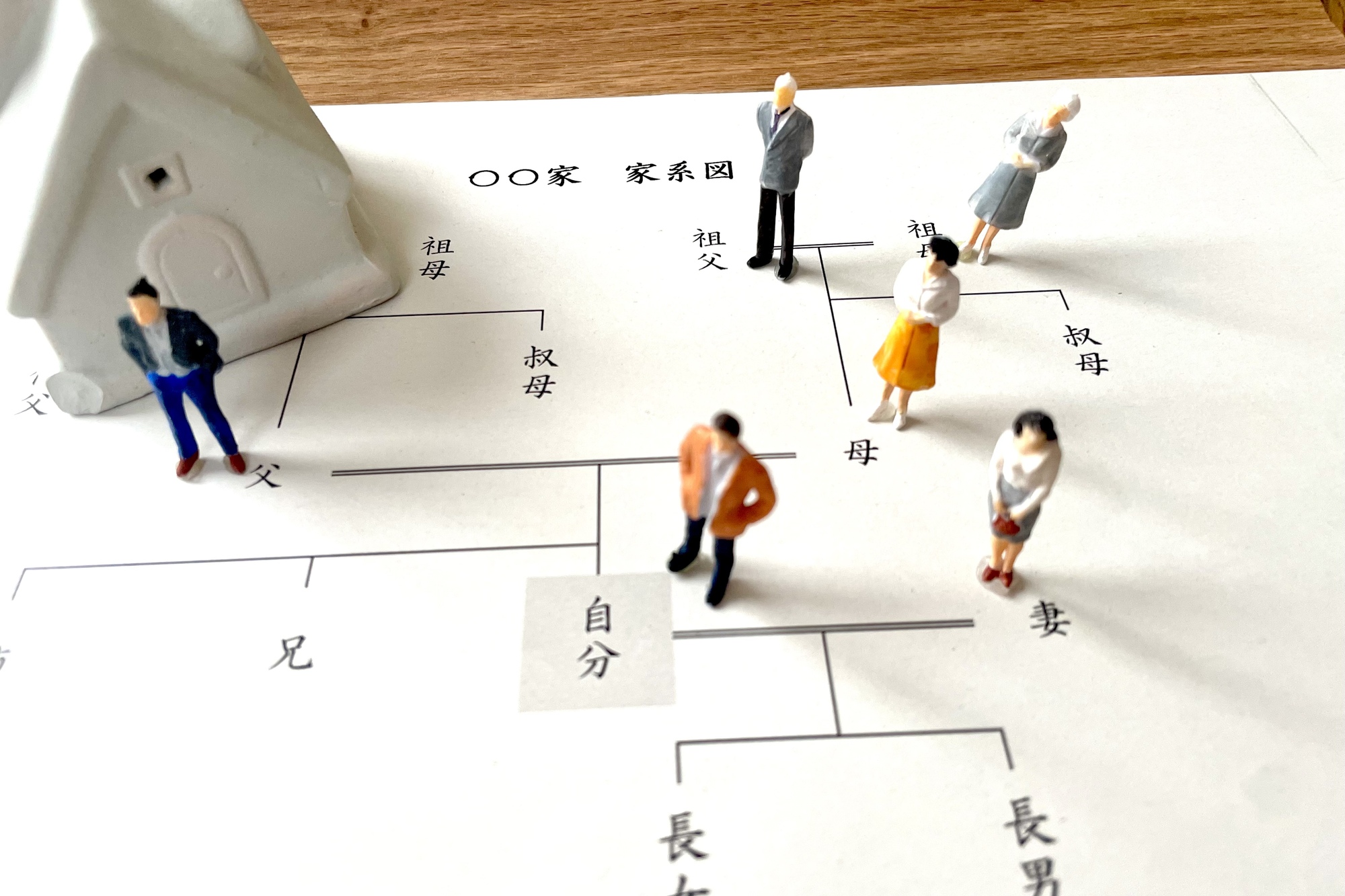
相続予定の土地などの不動産を、生前贈与で引き継ぐケースについてまとめます。
①相続時のトラブルを避けたい時
贈与は被相続人と贈与を受ける人(受贈者)の合意のみで成立できるため、誰に土地を引き継ぐかを自分で決められるメリットがあります。
また、遺留分の侵害に注意する必要がありますが、贈与は相続人以外へも可能です。
将来の相続手続きで、相続人同士で揉めることが予想される場合は、生前贈与しておくことで、引き継ぎの際のトラブルを軽減できます。
②先に引き継ぐことで有効活用したい時
贈与は、被相続人が亡くなった時に発生する相続と異なり、好きなタイミングで土地を引き継ぐことができます。
例えば、現時点で所有者が土地を持て余している場合、贈与を受けることで受贈者が活用して収益を得られます。
また、所有者が元気なうちに生前贈与で財産を引き継いでおくことで、ご本人が病気や認知症などになった際にも売却などの対応がスムーズに行えるメリットもあります。
③親の不動産経営を承継したい時
親が経営するアパートなどの収益物件を引き継ぐ予定なら、生前贈与を受けることで相続財産を減らせて、さらに家賃収入で相続税の支払いに備えられます。
また、賃貸物件が建っている土地は「貸家建付地の評価減」の特例が適用されるため、贈与税の負担も抑えられます。
土地を生前贈与と相続で引き継ぐそれぞれのメリットは以下のコラムで詳しく解説していますので合わせてお読みください。
〈関連コラム〉
土地は生前贈与と相続のどちらが得?メリット・デメリットや税金・手続きにかかるコストシミュレーションを紹介
④土地の評価額の大きな上昇が見込まれる時
土地の生前贈与を受ければ、その時点での評価額で贈与税が課税されます。仮に、相続時に土地の価値が大きく上がっていた場合、相続税が高額になってしまいます。
周辺の開発が進んでいるなど、土地の評価額の大きな上昇が見込まれる時は、先に贈与を受けることで税負担を抑えられる場合があります。
土地の贈与税の計算方法

贈与税の計算方法は以下の2通りがあります。
| 計算方法 | 概要 |
|---|---|
| ①暦年課税制度 | 個人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産に対して贈与税が課税される方式 |
| ②相続時精算課税制度 | 相続財産に、生前贈与を受けた財産分を合算した額に対して相続税が課税される方式 ※60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与する場合などの要件あり |
上記のうち、②の相続時精算課税については相続税のルールで計算されますので、今回は①の暦年課税制度で贈与を受けた場合の計算方法を解説します。相続時精算課税制度についてはコラムの後半で詳しく解説しています。
暦年課税制度で贈与を受けた場合、贈与税の基礎控除額は1年間あたり110万円で、年間110万円までの贈与なら贈与税はかからず、申告も不要です。
贈与が1年間で110万円を超えた場合は、以下の計算式で贈与税が算出されます。
(贈与税の課税対象金額 – 110万円)×(税率)-(控除額)=(贈与税額)
贈与税の税率および控除額は、以下のように一般贈与財産用と特例贈与財産用の2種類があります。
〈一般贈与財産用(一般税率)〉
兄弟間や夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
〈特例贈与財産用(特例税率)〉
18歳以上の受贈者が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合に使用します。祖父から孫、父から子への贈与などがあてはまります。
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
(参考)国税庁ホームページ|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
例えば、子が親から評価額5,000万円の土地の贈与を受けた場合は「特例税率」が適用され、贈与税は以下のように算出できます。
(5,000万円 – 110万円)× 55% – 640万円 = 2,050万円
上記のように、評価額の高い土地を暦年課税で一度に生前贈与を受けると、贈与税の負担が重くなってしまいます。
土地を生前贈与と相続で引き継いだ場合の、それぞれの税額シミュレーションは以下のコラムで詳しく解説していますので合わせてお読みください。
〈関連コラム〉
土地は生前贈与と相続のどちらが得?メリット・デメリットや税金・手続きにかかるコストシミュレーションを紹介
次章では、土地の贈与を受けた際の贈与税を非課税にする、または節税する方法について解説していきます。
土地の贈与税がかからない・節税する方法

土地などの不動産の生前贈与を受けた際の贈与税がかからないようにする方法や、節税する方法は以下の3つがあります。
- ①相続時精算課税制度を利用する
- ②居住用不動産の配偶者控除を活用する
- ③土地の持分を少しずつ贈与する
1つずつ方法や注意点を解説していきますね。
相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度とは、相続財産に「生前贈与を受けた財産分」を合算した額に対して相続税が課税される制度です。
相続時精算課税制度には非課税枠があり、生前贈与を受けた財産のうち基礎控除110万円+2,500万円分まで贈与税がかかりません。その代わりに、相続時に贈与分を相続財産にプラスして相続税が計算されます。
相続時精算課税制度を選択するには、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与する場合など、一定の要件が必要です。親子間や祖父母と孫など、近親者同士の贈与ならではの節税方法と言えます。
例えば、親から評価額2,500万円の土地を一度に暦年課税で贈与を受けると贈与税が発生しますが、翌年の確定申告で相続時精算課税制度を選択すると、贈与税を支払わずに済みます。
また、制度を使って贈与税が非課税になった贈与財産は相続時に相続税の計算に含まれますが、その他の相続財産と合わせて相続税の基礎控除額※以下なら、相続税もかかりません。
※相続税の基礎控除=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
(参考)国税庁ホームページ|No.4103 相続時精算課税の選択
- 親の土地にマイホームを建てたい
- 相続予定で使っていない土地を活用して収益を得たい
上記のように、相続前に土地を活用したい場合に、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けることで、贈与税・相続税対策ができます。
ただし、相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択できますが、一度選択すると同じ人からの贈与については暦年課税を選べない点に注意が必要です。
居住用不動産の配偶者控除を活用する
贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産または居住用不動産購入用資金の贈与が行われた場合、贈与税の計算の際に基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除できる特例で、「おしどり贈与」とも呼ばれます。
居住用不動産とは、贈与を受けた配偶者のマイホームまたはマイホーム用の土地を指し、土地は借地権も対象に含まれます。
居住用不動産の配偶者控除を利用できる主な要件は以下の通りです。
- 婚姻期間20年を過ぎた夫婦間の贈与であること
- 贈与を受けた翌年3月15日までに配偶者が住んでいて、その後も住み続ける見込みであること
なお、条件を満たせば、マイホームが建つ土地のみ贈与を受けて、配偶者控除を適用することもできます。
(参考)
国税庁ホームページ|No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
国税庁ホームページ|No.4455 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
マイホームを配偶者に贈与すると贈与者の遺産が少なくなるため、夫婦の財産に偏りがある場合などに相続税対策としてメリットが大きい特例です。
土地の持分を少しずつ贈与する
暦年贈与は不動産にも使えるので、土地の持分(所有権)を毎年少しずつ贈与し、最終的に所有権を全て移転することで節税が可能です。
所有権の移転中は贈与者と受贈者の共有状態になり、登記事項証明書には「100分の20」などそれぞれの持分比率が記載されます。
ただし、毎年決まった金額・時期などに贈与することで税務署から「定期贈与」と見なされた場合、一度に贈与を受けた場合の贈与税が課税される可能性があります。
暦年贈与で贈与税を節税するには、贈与契約書を毎年締結するなどの工夫も必要になるため、検討する場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
生前贈与で土地を引き継ぐ際の注意点

最後に、生前贈与で土地などの不動産を引き継ぐことを検討する場合に知っておきたい注意点を紹介します。
亡くなる一定期間以内の贈与は相続税の課税対象になる
被相続人が亡くなる前の一定期間以内に暦年贈与を受けた財産は、「生前贈与加算」の対象となり、相続税の課税対象になる点に注意しましょう。
〈生前贈与加算の対象となる贈与財産(令和6年1月1日以降の贈与)〉
| 相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日~令和9年12月31日 | 相続開始前3年以内 + 令和6年1月1日~令和6年12月31日の贈与 |
| 令和10年1月1日~令和10年12月31日 | 相続開始前3年以内 + 令和6年1月1日~令和7年12月31日の贈与 |
| 令和11年1月1日~令和11年12月31日 | 相続開始前3年以内 + 令和6年1月1日~令和8年12月31日の贈与 |
| 令和12年1月1日~令和12年12月31日 | 相続開始前3年以内 + 令和6年1月1日~令和9年12月31日の贈与 |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内 |
※上記は簡略化した表現です。正確には、加算期間は相続開始日から遡って計算されます。
(参考)国税庁ホームページ|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
上記のように、令和8年12月31日までに相続開始した場合、被相続人が亡くなる前(相続開始前)3年以内の暦年贈与は、相続税の課税対象になります。
加算対象期間内に贈与されていれば、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算されるため、暦年贈与の基礎控除(110万円)以内の贈与であっても、相続時に相続財産に加算されます。
※二重課税を避けるため、「加算された贈与財産に対する贈与税額は、加算された人の相続税の計算では控除されることになっています。
例えば、贈与税対策として、親から暦年課税の基礎控除以内で土地の持分を少しずつ贈与していても、加算対象期間内に親が亡くなってしまった場合は、贈与分が相続税の課税対象になります。
※ただし、例外として加算対象にならない贈与もあります。 (例:夫婦間の居住用不動産の贈与(おしどり贈与)の特例を受けた部分や、相続または遺贈によって財産を取得しなかった人への贈与などは加算対象外です)
つまり、相続が発生した時期によっては、贈与財産にも相続税がかかり、結果的に節税につながらない可能性があるため、税金対策としての生前贈与は計画的に行う必要があります。
贈与税以外に不動産取得税と登録免許税がかかる
土地などの不動産の贈与を受けると、贈与税の他に「不動産取得税」および「登録免許税」もかかります。
それぞれの税率は以下の通りです。
| 贈与で取得した不動産の不動産取得税 |
※宅地は建物を建てるための土地を指し、主に住宅や商業施設などの用途に利用される土地。農地などは対象外。 |
|---|---|
| 贈与で取得した不動産の登録免許税 |
|
(参考)
一方、相続人が相続で取得した不動産の不動産取得税は非課税であり、登録免許税の税率は0.4%と贈与よりもかなり低く設定されています。
例えば、評価額5,000万円の土地を贈与で取得した場合、不動産取得税は5,000万円×1/2×3%=75万円、登録免許税は5,000万円×2%で100万円となり、合計で175万円になります。
一方、相続で取得した場合は登録免許税が5,000万円×0.4%で20万円となり、贈与よりも負担が少なくなります。
生前贈与を検討する際は、ご自身のケースで不動産取得税や登録免許税の税額をシミュレーションしておくことをおすすめします。
まとめ
土地の贈与を受ける際に贈与税がかからない方法や、節税する方法を紹介してきました。
どの方法が最適かは、贈与者の不動産を含めた財産状況や、受贈者の希望などによっても変わってきます。
土地などの不動産の生前贈与や賃貸経営の承継などを検討する際は、節税効果はもちろん、将来の活用方法も含めて相談できる、相続対策に精通した不動産会社に相談するのがおすすめです。
未来の財託では、お客様の資産状況やご希望から、不動産を中心に最適な移転方法や有効な節税対策をご提案します。売却や賃貸物件の建築、リノベーションによる活用など、さまざまな土地活用方法に対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

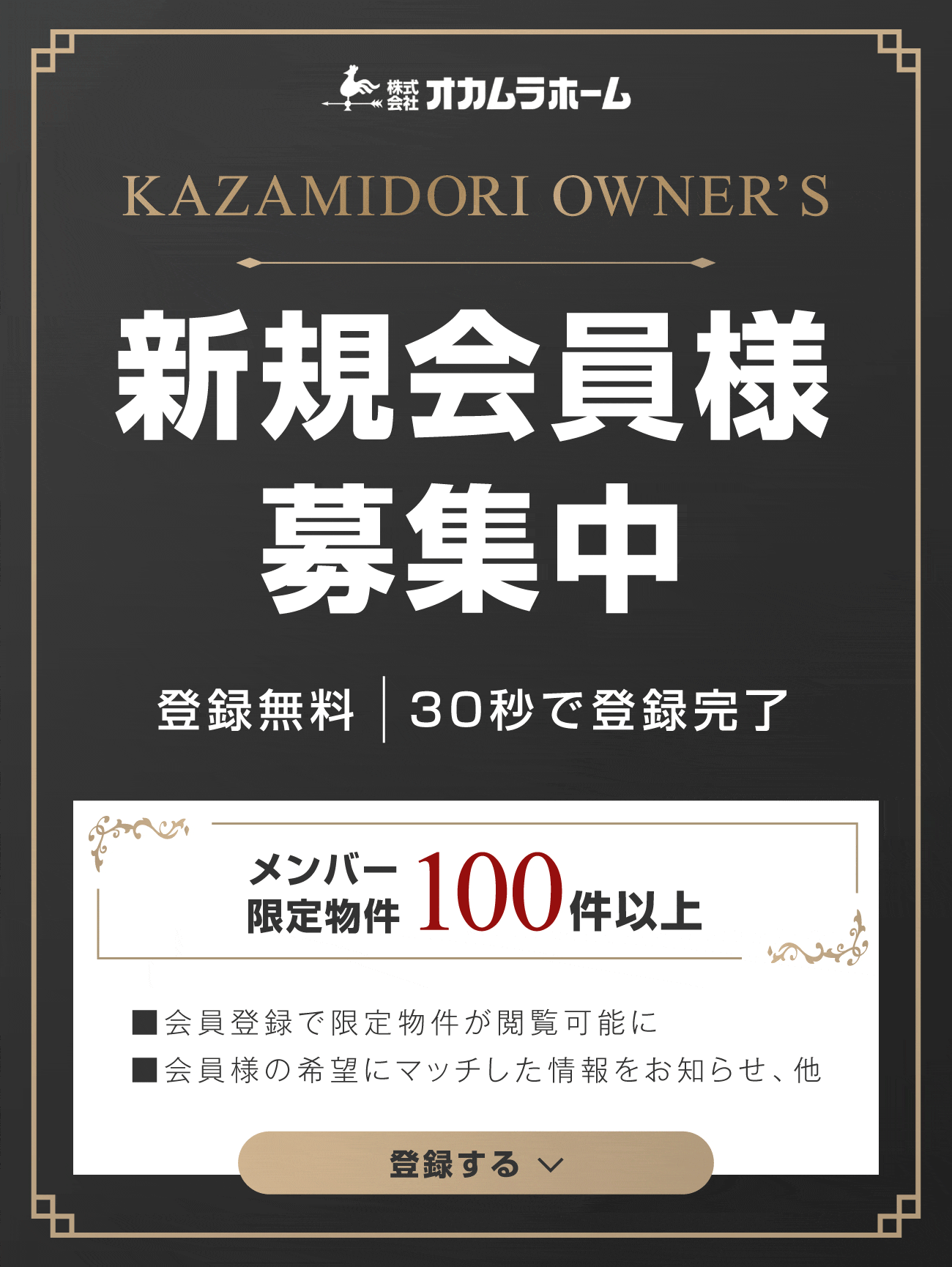

 0120-210-341
0120-210-341
